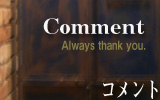『まだまだ暑い日が続くね。』といつもの常連さんと二人、話しながら同じウイスキーのソーダ割りを飲んでいた。そろそろ、閉店時間も近くなっていた。
「こんばんは!まだいいですか?」の声と同時に扉が開き一人の女性が入って来た。
『いらっしゃいませ!まだいいですよ!』と返事をし、カウンターの真ん中の席へ案内した。
『今、終わったの?』
「はい!今終わって・・・。マスターにプレゼントを持って来ました。」
『プレゼント?』
「20周年おめでとうございます!はい、これ・・・。」
『そんなに、気を使わなくてもいいのに・・・。』
「開けて見て下さい。あっ!その前に何か作ってもらおうかなぁ・・・。」
『そうですね。では、お任せでいいですか?』
「はい、楽しみ・・・。何が出てくるか・・・。」
この女性は、昔からお世話になっている同業で高校の後輩のKちゃんである。
彼女は、大の猫好きで、お店にはたくさんの猫の置物がバカラなどの高級グラスと一緒に置いてある素敵なお店のママである。
冷蔵庫からトムジンを出し、シェーカーに入れ、レモンジュースとシュガーシロップを加える。氷を入れて、シェイキングし、背の高いコリンズグラスに注いで、ソーダを加えて軽くステアする。レモンスライスとチェリーを飾れば出来上がりだ。
『はい!どうぞ!“トム・コリンズ”です。2杯作ったので、一緒に乾杯しましょう。』
「乾杯!おめでとうございます。」
『ありがとうございます。』
「トム・コリンズ? さっぱりしてて、美味しい・・・。」
『でしょ・・・。』
「どうしてこれを・・・?」
『このカクテルのベースは、トム・ジンという物で普通のジンに少し甘みをつけてあるんですよ。トムとは、トムキャットで猫のことなんです。ラベルにも猫の絵が描いてあるでしょう。』
「ホント!私が猫好きだからですね。」
『はい、そうです。』
と話しが弾んでる時に、常連さんからお代わりの催促があった。
『氷を鳴らさなくても、分かりますよ!』
「ほんと?気付いてないんじゃないかと思って・・・。」
『で、同じのでいいの?』
「いや、マスター!僕にも“トム・コリンズ”をちょうだい!」
『珍しいね。違うのを飲むなんて・・・。』
「実はね。猫を飼ってたんですよ!」
『それは、初耳だね。』とやり取りしながら、いつもの常連さんに、初めてカクテルを出した。そして、カウンターの真ん中へ戻った。
「マスター。開けて見て下さい。」
『そうですね。忘れるところでしたよ。』と奇麗にラッピングされた箱を開けた。
そこには、水彩画で描かれ、額に入れられた僕の自画像が入っていた。
『すごいですね。自分の自画像をいただくなんて・・・。』
「知り合いの画家に描いてもらいました。」
『よく特徴をとらえてますね。20年の歴史ですね。ほんと、ありがとうございます。』
「いいえ。喜んでもらえて嬉しいです。」
『絵は、大事にお店に飾らせていただきます。』
「あら、もう2時を回りましたね。帰らなくては・・・。」
『わざわざ、ありがとうございます。』
「トム・コリンズでしたっけ・・・。美味しかったです。次回からは、ウイスキーの前にこれをいただくことにします。」
『かしこまりました。』と店の外までお見送りをして、カウンターの中に戻った。いつもの常連さんが何か言いたそうな顔をしてた。
「ねぇ、マスター聞いてくれる?」
『手短にね・・・。閉店時間過ぎてるから。』
「分かってますよ。それがね飼ってた黒猫が居なくなったんですよ・・・。」
『猫にも逃げられたんですか。』
「そんなに言わなくても・・・。猫の話しを聞いて思い出しただけです。」
『きっと、いい彼でもできたんだよ。』
「そのうち、戻って来るだろうと待ってるけどね。」
『あなたも早く彼女を見つけないと・・・。』
「わ、分かってますよ。もう・・・。」