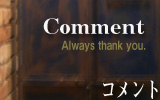2009年、新しい年になって、一ヵ月半が過ぎた。いつもの常連さんは、今年も変わらず、いつもの席で、いつものように一人だ。唯一変わったのは、ウイスキーのソーダ割りを“ハイボール”という名前で、注文するようになったことぐらいである。
「マスター!」と角の席から声がした。
『はい!何でしょう?』
「ハイボール!お代わり!」
『はい!今日は、いつもよりピッチが早いんじゃないの?』
「だって、今年もマスターの相手をしないといけないと思うとね。」
『言うよねぇ!それは、こっちの台詞です!』と返して、ハイボールのお代わりをつくろうとしていたときに、扉の開く音がした。
『いらっしゃいませ!』と扉の方へ声を出した。
「お久しぶりです・・・。」と言いながら一人の女性が入って来た。
『あぁ。ホントですね。お久しぶりです。どうぞ、お好きなところへ』とご案内した。
「二年ぶりかしら・・・。」
『もう、2年経ったんですね。ところで、何にしましょうか?』
「じゃぁ、あの頃よく飲んでいたのにしようかな・・・。」
『かしこまりました。』と返事をして、あの頃お出ししたカクテルを思い出しながら、バック棚からアマレットのリキュールと冷凍庫からウオッカを出してカウンターの上に並べた。そして、ハイボール用のウイスキーも取り出した。
アマレットは、アーモンドをしのばせる甘い香りのリキュールだが、主原料になっている杏の核が芳香成分となっている。
さて、カクテルをつくることにしよう。ロックグラスに大き目の氷をひとつ入れ、ウオッカとアマレットを注ぎ、バースプーンでステアすると出来上がりだ。いたってシンプルで簡単なカクテルではあるが、そんなに弱いカクテルでもない。
『はい!どうぞ。“ゴッドマザー”です。』と言って、その女性の前のコースターの上に静かに運んだ。それから、ハイボールのお代わりをつくり、角の席へ運び、その女性の前に戻った。
「そう、これでしたね。」と声が聞こえ、小さい手でグラスを持ち、口まで運んだ。
「美味しい!この甘さと香りがなつかしい・・・。でも、意外と強い・・・。」
『そうですね。女性に人気のあるカクテルなんですけど、そんなに弱くはないですよ。』
「ですね・・・。あの頃と比べたら少し弱くなったみたい・・・。」
と話した後、しばらく静かな空気が流れ、耳には、ヘレンメリルの“YOU'D BE SO NICE TO COME HOME TO”が聞こえてきた。ちょっとハスキーな歌声がなんともいえないこの場の雰囲気を作り出してくれている。
そして、また女性から声が聞こえた。
「マスター。あの頃、このカクテルにいっぱい元気をもらいました。ちょうどバツイチになったばかりで・・・。」
『そうでしたか。“ゴッドマザー”という名前が、元気をくれたんですね。』
「はい。それと、マスターがたくさん愚痴を聞いてくれたお陰です。」
『聞き役も、バーテンダーの仕事のひとつですから!』
「それに、二年という時が、鍛えてくれたし、下の子も中学生になって、やっと落ち着くことが出来て、ここにも来れるようになり、お礼も言いたくて・・・。」
『お礼だなんて・・・。ただカクテルを選んで、お話しを聞いただけです。バーテンダーとして当たり前のことですよ。』
「そうであっても、私にとっては・・・。」と声がしたあと、残りのカクテルを飲み干した。そして、また女性の口が動いた。
「ここに来ると、元気になれるし、辛いことも忘れることが出来ます・・・。美味しかった!また、おじゃましますね。」
『ありがとうございます。また、よろしくお願いします。』と挨拶をして、扉の外まで見送りをし、カウンターの中に戻った。
ロックグラスの中には、半分ほどに小さくなった氷だけが残っていた。それを片付け、常連さんの空のグラスも下げて、新しいハイボールを造つくり角の方へ運んだ。
「マスター!バツイチって、大変なんだね・・・。」
『結婚よりも、エネルギーを使うというからね。でも、彼女に限らず、みんな頑張ってるんですよ。あなたも頑張らないと・・・。』
「分かってますよ!でも、女性って強いよね。」
『そうね。強くなるんですよ。いろんな意味で・・・。』
「でも、何か寂しそうだった?」
『そんなとこまで、分かったの!でも、あなたの方がもっと寂しそうに見えるけどね。』
「だったら、何とかして下さいよ!」
『強くなろうね!』
「えぇ。。。」