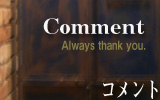「遅いなぁ」とBARには珍しく三つもある時計を見渡して、独り言を言っていた。
10時には来ると昨夜電話でそう言っていたはずなのに、と少しイライラとどこか緊張しているようで落ち着かない。何年振りだろうか、いつもカウンターの決まった場所に座り、ハイボールしか飲まない、いやハイボールしか知らないのだろう“いつもの常連さん”ちゃんと指定席は空けて待っているのに…。
と、時計を何度も見ながら、思いを募らせていた時に、ドアがゆっくりと開く音がした。
『こんばんは…。』と確かに聞き覚えのある声に入口の方を向いて声を返した。
「いらっしゃいませ!」
『マスター!』
「おぅ…。お、遅かったじゃないですか!」
『良かった。安心しましたよ。元気そうで、そして、開いててよかった。』
「約束は10時だったはずよね。」
『まぁ、いいじゃないですか。久しぶりに佐賀に帰ってきたんだし、佐賀時間ですよ。』
「相変わらずだね。だから、彼女にフラれるんですよ。でも、ホッとしましたよ。変わってなくて…。」
『店…。閉まってしまったんじゃないかと、心配してましたよ。』
「ありがとうございます。余計なお世話です。お客様は、あなただけじゃないから大丈夫ですよ。」と、久しぶりのこのやり取りで盛り上がり、いつもの常連さんは、もう、コースターがセットされているいつもの席に座り、予定通りのハイボールのオーダーである。
バック棚からいつものウイスキーを取り、カウンターに置いた。そして、グラスを二個用意し、それぞれに氷を入れ、ハイボールをつくり、一つは、コースターの上に運び、もう一つは自分で持って、カウンターの隅へ動いた。
「乾杯といきますか!」
『マスターも飲むの?』
「あたりまえじゃないですか!今日はあなたのために貸切です。」
『そ、そうなの。じゃぁ、乾杯!』
「乾杯!」
『で、何に乾杯だっけ?僕は、フラれて帰ってきたし、この店は暇でつぶれそうだし…。』
「もう!あなたとわたしの物語がまた始まることにですよ。」
『どういうこと…。』
「まぁ、いいじゃないの。」
そう返し、少し顔がほころんでる自分と、ニコニコ顔のいつもの常連さん、そして、あの頃の空気にいつしか戻っているような気がしてきた。BARは人で空気が変わるもの、その空気をうまくコントロールするのもバーテンダーの仕事の一つだと教わったのも思い出した。
「ところで、あの彼女とは、どうなったの?フラれたとか言っているけど。」
『彼女は、忙しいのが好きなんですよ。そのペースを乱したくないし、楽しそうに仕事している姿が好きなんですよね…。だから、僕から…。』と言いかけた時に、扉が開く音がした。
「いらっしゃいませ!」と入口の方を向いて、頭を下げて声を出した。一人の女性がゆっくりと入って来た。
『まだ、大丈夫ですか?もう、閉店じゃ…。』
「いえいえ、まだ、大丈夫ですよ。」とカウンターの常連さんとは反対の隅へ案内し、オシボリを渡し、コースターを置き、メニューを差し出した。
『あのう、マルスウイスキーの“ラッキーキャット”はありますか?』
「はい。ありますよ。」
『それを、ハイボールにしてください。』
「はい、かしこまりました。」
バック棚から、ラベルにネコの写真が描かれているボトルを取出した。これは、信州マルス蒸留所から1,200本限定で発売されたブレンデッドウイスキーで、ポートワインとマディラワインの空き樽に2年間後熟したものをヴァッティングしたものだ。甘くエキゾチックな味わいが特徴的なウイスキーだと言われている。
「はい、どうぞ。」と、そのウイスキーでつくったハイボールを女性の前のコースターの上に運んだ。
『あぁ、美味しい…。甘さがあって、香りもよくて。ありがとうございます。』
「どういたしまして。ところで、どうしてこのウイスキーを?」
『私、ネコが大好きなんです。たまたま、ネットで見つけて、飲んでみたいなぁと思って、ここならあるんじゃないかと。』
「そうでしたか。よかったですよ。もう少しで無くなるところでした。」そう言った後に、もう片隅の方へ身体を向けた。
「すみませんね。ほったらかして。」
『昔から、そうじゃないですか。久しぶりだというのに。まったくですよ。』
『マスター。そのネコのウイスキーで僕にもハイボールをちょうだい。』
「ご、ごめんね。もうほとんど入っていないんですよ。」とそのボトルを、いつもの常連さんの前に置いた。
『マスター。あと一杯分ぐらい入っているじゃないですか!』
「これは、テンシュノトリブン。」
『天使の取り分?』
「違いますよ。“店主”の取り分!」
『なんですか!お客様ですよ。僕は!』
「これが、私の楽しみなんです。我慢しなさい。」
と、いつもの常連さんとカランでいるときに、女性から声が聞こえた。
『マスター、ご馳走様でした。飲めてよかったです。』と言った後に、大きく息を吸って、また、口が動き始めた。
『実は、今年いっぱいで仕事を辞めて、結婚するんです。』
「それは、おめでとうございます。」
『ただ、彼はサラリーマンですが、実家が喫茶店をやっていて、その店を手伝うことになっているんです。それに、少し迷いがあって、でも、決めました。喫茶店で頑張って、“ラッキーキャット”になろう。て…。』
「なれますよ。きっと、幸せの招き猫に…。」
『ありがとうございます。』
「こちらこそ、ありがとうございました。」と、女性を扉の外まで見送り、カウンターの中に戻った。
『マスター!飲ませてくださいよ。』といつもの常連さんから声が飛んできた。
「ちょっと待って、確かさっき、何か言いかけてなかったっけ。」
『もう、忘れました!それより、気付いてくださいよ。僕がこの店の招き猫なんですよ!昔も今も…。』
「そうかもね…。」
10時には来ると昨夜電話でそう言っていたはずなのに、と少しイライラとどこか緊張しているようで落ち着かない。何年振りだろうか、いつもカウンターの決まった場所に座り、ハイボールしか飲まない、いやハイボールしか知らないのだろう“いつもの常連さん”ちゃんと指定席は空けて待っているのに…。
と、時計を何度も見ながら、思いを募らせていた時に、ドアがゆっくりと開く音がした。
『こんばんは…。』と確かに聞き覚えのある声に入口の方を向いて声を返した。
「いらっしゃいませ!」
『マスター!』
「おぅ…。お、遅かったじゃないですか!」
『良かった。安心しましたよ。元気そうで、そして、開いててよかった。』
「約束は10時だったはずよね。」
『まぁ、いいじゃないですか。久しぶりに佐賀に帰ってきたんだし、佐賀時間ですよ。』
「相変わらずだね。だから、彼女にフラれるんですよ。でも、ホッとしましたよ。変わってなくて…。」
『店…。閉まってしまったんじゃないかと、心配してましたよ。』
「ありがとうございます。余計なお世話です。お客様は、あなただけじゃないから大丈夫ですよ。」と、久しぶりのこのやり取りで盛り上がり、いつもの常連さんは、もう、コースターがセットされているいつもの席に座り、予定通りのハイボールのオーダーである。
バック棚からいつものウイスキーを取り、カウンターに置いた。そして、グラスを二個用意し、それぞれに氷を入れ、ハイボールをつくり、一つは、コースターの上に運び、もう一つは自分で持って、カウンターの隅へ動いた。
「乾杯といきますか!」
『マスターも飲むの?』
「あたりまえじゃないですか!今日はあなたのために貸切です。」
『そ、そうなの。じゃぁ、乾杯!』
「乾杯!」
『で、何に乾杯だっけ?僕は、フラれて帰ってきたし、この店は暇でつぶれそうだし…。』
「もう!あなたとわたしの物語がまた始まることにですよ。」
『どういうこと…。』
「まぁ、いいじゃないの。」
そう返し、少し顔がほころんでる自分と、ニコニコ顔のいつもの常連さん、そして、あの頃の空気にいつしか戻っているような気がしてきた。BARは人で空気が変わるもの、その空気をうまくコントロールするのもバーテンダーの仕事の一つだと教わったのも思い出した。
「ところで、あの彼女とは、どうなったの?フラれたとか言っているけど。」
『彼女は、忙しいのが好きなんですよ。そのペースを乱したくないし、楽しそうに仕事している姿が好きなんですよね…。だから、僕から…。』と言いかけた時に、扉が開く音がした。
「いらっしゃいませ!」と入口の方を向いて、頭を下げて声を出した。一人の女性がゆっくりと入って来た。
『まだ、大丈夫ですか?もう、閉店じゃ…。』
「いえいえ、まだ、大丈夫ですよ。」とカウンターの常連さんとは反対の隅へ案内し、オシボリを渡し、コースターを置き、メニューを差し出した。
『あのう、マルスウイスキーの“ラッキーキャット”はありますか?』
「はい。ありますよ。」
『それを、ハイボールにしてください。』
「はい、かしこまりました。」
バック棚から、ラベルにネコの写真が描かれているボトルを取出した。これは、信州マルス蒸留所から1,200本限定で発売されたブレンデッドウイスキーで、ポートワインとマディラワインの空き樽に2年間後熟したものをヴァッティングしたものだ。甘くエキゾチックな味わいが特徴的なウイスキーだと言われている。
「はい、どうぞ。」と、そのウイスキーでつくったハイボールを女性の前のコースターの上に運んだ。
『あぁ、美味しい…。甘さがあって、香りもよくて。ありがとうございます。』
「どういたしまして。ところで、どうしてこのウイスキーを?」
『私、ネコが大好きなんです。たまたま、ネットで見つけて、飲んでみたいなぁと思って、ここならあるんじゃないかと。』
「そうでしたか。よかったですよ。もう少しで無くなるところでした。」そう言った後に、もう片隅の方へ身体を向けた。
「すみませんね。ほったらかして。」
『昔から、そうじゃないですか。久しぶりだというのに。まったくですよ。』
『マスター。そのネコのウイスキーで僕にもハイボールをちょうだい。』
「ご、ごめんね。もうほとんど入っていないんですよ。」とそのボトルを、いつもの常連さんの前に置いた。
『マスター。あと一杯分ぐらい入っているじゃないですか!』
「これは、テンシュノトリブン。」
『天使の取り分?』
「違いますよ。“店主”の取り分!」
『なんですか!お客様ですよ。僕は!』
「これが、私の楽しみなんです。我慢しなさい。」
と、いつもの常連さんとカランでいるときに、女性から声が聞こえた。
『マスター、ご馳走様でした。飲めてよかったです。』と言った後に、大きく息を吸って、また、口が動き始めた。
『実は、今年いっぱいで仕事を辞めて、結婚するんです。』
「それは、おめでとうございます。」
『ただ、彼はサラリーマンですが、実家が喫茶店をやっていて、その店を手伝うことになっているんです。それに、少し迷いがあって、でも、決めました。喫茶店で頑張って、“ラッキーキャット”になろう。て…。』
「なれますよ。きっと、幸せの招き猫に…。」
『ありがとうございます。』
「こちらこそ、ありがとうございました。」と、女性を扉の外まで見送り、カウンターの中に戻った。
『マスター!飲ませてくださいよ。』といつもの常連さんから声が飛んできた。
「ちょっと待って、確かさっき、何か言いかけてなかったっけ。」
『もう、忘れました!それより、気付いてくださいよ。僕がこの店の招き猫なんですよ!昔も今も…。』
「そうかもね…。」