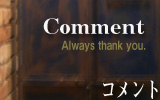『いらっしゃいませ!』と扉の開く音に反応し、声を入り口の方へ向かって投げかけた。
雨に頭と肩を濡らしたいつもの常連さんが、めずらしく女性と二人である。
『朝からずっと降ってるね・・・。』と声をかけ、いつもの席に案内した。
そして、女性の方には『初めまして・・・。』と挨拶をした。
「マスター!今日は、ひとりじゃないですよ!」
『まさか!彼女・・・?』
「だったら、いいけどね。今年入社の後輩で、彼女が帰る前にカクテルを飲みたいって言うもんだから・・・。」
『それは、どうもありがとうございます。』
「で、僕はいつもの! 彼女には、美味しいカクテルをお願いします!」
『はい!かしこまりました。』と返し、バック棚からいつものウイスキーをつかみ、二人のいるカウンターの上に置いた。そして、グラスに大きな氷を2個入れ、ウイスキーをそっと注ぎソーダを加えて、軽くステアし、いつもの常連さんのコースターの上に運んだ。
さて、カクテルは何をお出ししようかと考えていた時に、「マスター。」と小さな、可愛い声が聞こえた。
「私、雨女ってよく言われるんです。入社した日も、今日も雨・・・。でも、嫌いじゃないんですよ。今日みたいな雨は・・・。」とまだ少し濡れているストレートの髪を触りながら話しかけていた。
「マスター!雨の似合う女性のイメージで・・・。」と、いつもの常連さんの声が会話を遮り『わかってますよ!』と答えて、女性の方へ視線を移した後、冷凍庫からウオッカを、バック棚からバイオレットのリキュール(パルフェ・タムール)とブルーキュラソーを取り出し、絞りたてのグレープフルーツ・ジュースを冷蔵庫から出してカウンターの上に並べた。
シェーカーにその材料を入れ氷を加えて、振った。
静かな店内に透き通るようなシェイキングの音が響き、最もBARらしい空気に満ちた瞬間である。
シェーカーからカクテルグラスに注ぎ入れ、ブルーキュラソーをドロップして完成である。そのカクテルをゆっくりと女性のコースターの上に運んだ。
『はい。お待たせしました。どうぞ!』
「へぇ・・・。マスター、シェーカー振れるんだね!」
『当たり前です!』
と、いつもの常連さんとやり取りしてる間に、カクテルを一口すする音がした。
「美味しいです。それとこの色が好きです。」の後に少し間をおいて、「名前はなんですか?」と聞かれた。
『名前ですか?そうですね・・・。』と考える間もなく、「私が付けてもいいですか?」と、また、小さい声が返ってきた。
『どうぞ、お好きな名前を付けて下さい。』と話しかけた。女性は、カクテルグラスを持ち上げ、また一口飲み、こっちを向いた。
「あのぅ、“雨の物語”にしたいですけど、いいですか?」
『雨の物語ですか・・・。いいですね。それにしましょう。で、どうしてその名前なんですか?』
「実は・・・。私の母も雨が好きで、似てるんです。雨の日に出会って、雨の日に別れが来て・・・。よく聞かされてました。母の恋愛の話を・・・。」
『そうですか・・・。誰にも“物語”はあるものです。』
と答えた後、しばらくの間、静かな空気に包まれ、ふと昔を思い出していた。
確か、私にも似たようなことがあった。もう28年ぐらい前だろうか・・・。
付き合ってた女性から突然別れようと言われた日も、今日みたいな雨が降っていたような気がする。
その翌年に結婚したという噂が風の便りのごとく耳に入った。子供がいるとしたら、ちょうど、この女性ぐらいだろうか・・・。
と昔に浸っていたその時、現実に引き戻すような氷のなる音が聞こえた。
『お、お代わりは・・・?』
「いや、いいよ。彼女、帰る時間だし・・・。」
「美味しいカクテル、ありがとうございました。“雨の物語”母にも伝えときます。」
『・・・。よろしくお伝えください。ありがとうございます。』
『ちゃんとタクシーに乗せてあげて下さい!』といつもの常連さんに伝えた。
扉のしまる音がし、誰もいない静かな時間が訪れた。空のグラスを片付けながら、またあの頃の情景がよみがえろうとしていた、その時、扉が開いた。
「マスター!送ってきたよ!」
『も、戻ってきたんですか!』
「だって、マスター、何か寂しそうな顔してたし・・・。」
『そんなことないですよ・・・。偶然です。偶然・・・。』
「何が偶然なの?」
『何でもないです!ところで、これから私に付き合って下さい!』
「マスターに・・・。」
『歌いに行きますよ!歌いに・・・。』
「カ、カラオケ!ですか? 何、歌うんですか?」
『決まってるでしょ!“雨の物語”イルカの歌ですよ!』
「えぇー、僕、そんな世代じゃないけど・・・。」