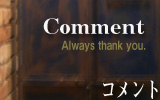『いらっしゃいませ!』と扉のほうに顔を向けた。いつもの常連さんが、何やらニコニコ顔で入って来た。
「マスター!明けましておめでとう。」
『おめでとうございます!今年もよろしくお願いします。ところで、何を浮かれた顔をしてるんですか?』
「それがね、お正月に初詣に行って、おみくじを引いたら“大吉”だったんですよ。」
『すごいですね。今年は良い年になったらいいね。で?何にしましょう!』
「もう、分かってるくせに・・・。いつものですよ。“ハイボール”」
『そうだったね。』と答え、バック棚からウイスキーを取り出し、ソーダ割りを作り、いつもの角の席のコースターの上に運んだ。
「ねぇ、ねぇ。聞いてよ!」と常連さんが話しかけた時に、また扉がゆっくり開き、一人の若い男性がなにやら、遠慮しがちな感じで入ってきた。
『いらっしゃいませ。どうぞ、空いてる席へ』と案内し、オシボリを渡し、コースターを置いた。
『何にしましょうか?』とたずねた後に付け足して、『メニューをお出ししましょう。』と言って、その男性に差し出した。
「あ、ありがとうございます。」と小声で答え、しばらく、メニューを見わたしていた。その間、いつもの常連さんの前に行った。
「未成年じゃないの?」と常連さんから合図があり、『違うと思うよ。』と合図を返した。
「す、すみません・・・。」と声が聞こえ、その男性の前に戻った。
『はい!お決まりですか。』
「マティーニを下さい。」
『マ、マティーニですね。かしこまりました。』
マティーニは、カクテルの王様と言われているもので、飲む人にも、造る人にもこだわりがあるカクテルだ。また、色んなエピソードもあり、マティーニだけで一冊の本が出来るぐらいなのである。イギリスの首相だったウィンストン・チャーチルは、執事にベルモットを口に含ませ、グラスに注いだジンに息を吹きかけさせて、超ドライなマティーニを飲んだとも言われている。
さて、今年最初のマティーニを造ることにしよう。まず、小皿にピンに刺したオリーブと丸く切り取ったレモンの皮を用意し、ミキシンググラスに氷を入れ、ベルモットを少し注ぎステアし、氷の角が取れミキシンググラスが冷えたらベルモットを捨てる。そして、ここからは手際よく、冷していたカクテルグラスを出し、ミキシンググラスにオレンジビタースを一振り加え、よく冷したジンとベルモットを注ぎステアする。カクテルグラスに注ぎ、オリーブを飾り、レモンピールを絞りかければ出来上がりだ。
『はい。どうぞ。』とその若い男性の前のコースターの上に静かに運んだ。
「こ、これがマティーニですね。」と呟き、一口喉に流し込んだ。
「き、キツイ、カクテルですね。しかも結構強いし・・・。」
『このマティーニは、“キング・オブ・カクテル”と言われているもので、辛口を代表するカクテルなんですよ。』
「ホント、大人の味ですね。僕には、まだこの美味しさが分からないや…。」
と言いながら、もう一口飲んだ。
『どうして、このカクテルを・・・。』とさり気なく聞いてみた。
「はい、実は、父が好きなカクテルなんです。いつも聞かされていたんです。
“大人になったらBARに行け”って“マティーニを飲んでみろ”って・・・。」
『そうですか。いいお父様ですね。でも、このカクテルの美味しさが分かるようになったのは、きっと、最近のことだと思いますよ。私も、初めて飲んだ時は、正直、美味しいとは思いませんでしたから・・・。』
「マスター。ありがとうございます。まだ20歳になったばかりの学生ですが、この街にいる間は、ここに通って、勉強することにします。」
『それは、嬉しいです! BARのファンが増えることは大歓迎ですよ。』
「マティーニが、どういうものか分かったし、今日はこれで帰ります。」
『ありがとうございます。実家にお帰りになった際は、お父様によろしくお伝え下さい。』
「はい、いいBARを見つけたと伝えます。」
と言って、入って来た時よりも、堂々とした感じで帰って行かれた。
カウンターの中に戻り、オリーブが残されたカクテルを片付け、いつもの常連さんの前に行った。
「未成年じゃなかったんだね。見かけも格好も若いし・・・。てっきり未成年かと思いましたよ。」
『あなたより、大人だったように感じたけどね。』
「ちょっと!僕より一回り以上も下なんだよ。彼は・・・。」
『今のあなたと同じ年頃になった時は、追い越されてますよ。きっと・・・。』
「それって、どういう意味なの!」
『素敵な女性と結婚してるかもよ・・・。』
「えぇ!だ、大丈夫ですよ!話しは戻るけど“大吉”だったんですよ。“縁談実る”て書いてあったもん・・・。」
『最後の神頼みですか・・・。』
「・・・。」