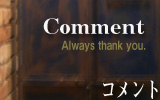時計は夜11時になろうとしている。久しぶりにあのBARへ向かっているが、あまり気乗りがしない。
もう今年も終わろうとしているのに、一緒に行きたいとずっと思っていた。マスターとママに会ってもらいたかったのに...
「お久しぶりです。」と重い扉を開け、静かに中に入った。
『あら、いらっしゃいませ!お元気でしたか?』とママの優しい笑顔が迎えてくれた。カウンターには一人の男性客がハイボールを飲んでいる。
後ろのテーブル席には、氷だけになったグラスが二つと、オシボリが二つそのまま残されていた。
「マスターは?」とカウンターの中のママに声をかけた。
『はい。すみませんね。マスターは膝を痛めて、まだ二階にいますよ。』
「大丈夫ですか?」
『大丈夫そうです。最近朝のウォーキングにハマっててね、無理しちゃったんですよ。』
「二階から降りてくるのが大変ですね。」
『そうなんです。私が一人でやるから休んだらと言ってるのに、15分ぐらいかけて降りてきますよ。』
「じゃあ、もうすぐですね。」
「あっ、ママ!ハイボールをください。」
『はい。かしこまりました。』
棚からグラスを出し、氷を入れる音が優しく響く。そこにウイスキーが注がれて、炭酸で満たされた。
泡のはじける音がリズミカルに聞こえてくる。
『はい。お待たせしました。私もハイボールも作れるようになりましたよ。あとビールもね。』
とママの声と同時に、白いコースターの上に運ばれてきた。
「おぉ、美味い!」「約半年ぶりですね。」
『そんなに経ちますか。』
「はい。いろいろあって来れなかったんですよ。」
『そうですか?私もハイボールの作り方とビールの出し方を教わって半年です。まだこの二つしかお出しできませんけどね。』
とやさしい笑顔でママが話しながら、カウンターの男性の会計をし、テーブル席の後片付けを始めたときに、小さい声がした。
『いらっしゃい!お久しぶりですね。』といつの間にかマスターがカウンターの中に立っていた。そして奥で“ミャー”と鳴き声が聞こえた。
「マスター、大丈夫ですか!」
『大丈夫ですよ。ちょっと無理して7キロも頑張ったら、膝が痛み出してね。ブロック注射を2回打ってもらったから、だいぶ歩けるようになりましたよ。』
「無理はだめですよ!」
『そうですね。ここのところ二階にいる時間が長くて、猫の世話は僕の担当になりました。』とマスターが話した後、返すようにママから声がした。
『いいえ、猫がマスターの世話をしてくれてますよ。今まで下に降りてこなかった猫がねぇ、マスターについて階段を下りてくるようになったんですよ。』
「あぁ、だからさっき、声がしたんですね。かわいい小さい鳴き声でした。」
『はい。チョコンと顔出して、ミャーと鳴いて二階へ帰っていきますよ。』とママが返した。
「マスター、猫に介護されてますね。」
『はい。そのようで...。』
「でも、良かったです。久しぶりにお二人のお顔が見れて。」
『ありがとうございます。』
「マスター。最後にもう一杯いただこうかなぁ。」
『はい。かしこまりました。』
と、ゆっくりとした動作でバック棚から1本のウイスキーを取り、僕の前に置き、またゆっくりとした動きでストレートグラスが二つ運ばれてきた。
『一緒に飲みましょう。”イチローズモルト秩父ピーテッド”です。やっと手に入れたんですよ。』
「これは、貴重なウイスキーじゃないですか!」
グラスに注がれた琥珀色のウイスキーが空になったグラスと代えられてコースターの上に置かれた。
そのグラスからほのかにスモーキーさが漂ってきた。
「マスター。乾杯!いただきます!」
『お久しぶりです。かんぱい。』
「おぉ、美味い!度数は少し高めですね。そしてこのスモーキーな味が、何かいろんなことをかき消してくれますよ。さすがのチョイスです。」
『いいでしょう。日本のウイスキーもここが出来てから人気が高まってきたんですよ。』
「あっ、ママも一緒に乾杯したいけど。」
『すみません。例の…』
「そっか、猫の世話ですね。」
「今日は、来てよかったです。何か吹っ切れました。」
『それは、良かったです。きっと彼女さんも気にされていますよ。』
「うん。な、なんで分かるんですか!フラれたことを…」
『はい。なんとなくね。』
「クリスマスが近いこの時期に、フラれるなんて悲しすぎますよね。」
『ここがあるじゃないですか。この冬は、ここで暖まってください。』
「・・・・。」
ほんとに暖まるBARだ。このお店に通うようになれてよかったと思う。マスターとママの絶妙なバランスがとても癒されるし、元気をもらえる。もっと早く来ればよかったかもしれない。
「もうこんな時間ですね。閉店の12時を過ぎてました。すみません。」とマスターに声をかけた時に、奥の方から”ミャー”とまた小さな鳴き声が聞こえた。
『お迎えが来たようです。これで閉店します。二階に戻るのにまた15分はかかりますからね。』
「マスター。ありがとうございます。暖まりにまた来ます。」
もう今年も終わろうとしているのに、一緒に行きたいとずっと思っていた。マスターとママに会ってもらいたかったのに...
「お久しぶりです。」と重い扉を開け、静かに中に入った。
『あら、いらっしゃいませ!お元気でしたか?』とママの優しい笑顔が迎えてくれた。カウンターには一人の男性客がハイボールを飲んでいる。
後ろのテーブル席には、氷だけになったグラスが二つと、オシボリが二つそのまま残されていた。
「マスターは?」とカウンターの中のママに声をかけた。
『はい。すみませんね。マスターは膝を痛めて、まだ二階にいますよ。』
「大丈夫ですか?」
『大丈夫そうです。最近朝のウォーキングにハマっててね、無理しちゃったんですよ。』
「二階から降りてくるのが大変ですね。」
『そうなんです。私が一人でやるから休んだらと言ってるのに、15分ぐらいかけて降りてきますよ。』
「じゃあ、もうすぐですね。」
「あっ、ママ!ハイボールをください。」
『はい。かしこまりました。』
棚からグラスを出し、氷を入れる音が優しく響く。そこにウイスキーが注がれて、炭酸で満たされた。
泡のはじける音がリズミカルに聞こえてくる。
『はい。お待たせしました。私もハイボールも作れるようになりましたよ。あとビールもね。』
とママの声と同時に、白いコースターの上に運ばれてきた。
「おぉ、美味い!」「約半年ぶりですね。」
『そんなに経ちますか。』
「はい。いろいろあって来れなかったんですよ。」
『そうですか?私もハイボールの作り方とビールの出し方を教わって半年です。まだこの二つしかお出しできませんけどね。』
とやさしい笑顔でママが話しながら、カウンターの男性の会計をし、テーブル席の後片付けを始めたときに、小さい声がした。
『いらっしゃい!お久しぶりですね。』といつの間にかマスターがカウンターの中に立っていた。そして奥で“ミャー”と鳴き声が聞こえた。
「マスター、大丈夫ですか!」
『大丈夫ですよ。ちょっと無理して7キロも頑張ったら、膝が痛み出してね。ブロック注射を2回打ってもらったから、だいぶ歩けるようになりましたよ。』
「無理はだめですよ!」
『そうですね。ここのところ二階にいる時間が長くて、猫の世話は僕の担当になりました。』とマスターが話した後、返すようにママから声がした。
『いいえ、猫がマスターの世話をしてくれてますよ。今まで下に降りてこなかった猫がねぇ、マスターについて階段を下りてくるようになったんですよ。』
「あぁ、だからさっき、声がしたんですね。かわいい小さい鳴き声でした。」
『はい。チョコンと顔出して、ミャーと鳴いて二階へ帰っていきますよ。』とママが返した。
「マスター、猫に介護されてますね。」
『はい。そのようで...。』
「でも、良かったです。久しぶりにお二人のお顔が見れて。」
『ありがとうございます。』
「マスター。最後にもう一杯いただこうかなぁ。」
『はい。かしこまりました。』
と、ゆっくりとした動作でバック棚から1本のウイスキーを取り、僕の前に置き、またゆっくりとした動きでストレートグラスが二つ運ばれてきた。
『一緒に飲みましょう。”イチローズモルト秩父ピーテッド”です。やっと手に入れたんですよ。』
「これは、貴重なウイスキーじゃないですか!」
グラスに注がれた琥珀色のウイスキーが空になったグラスと代えられてコースターの上に置かれた。
そのグラスからほのかにスモーキーさが漂ってきた。
「マスター。乾杯!いただきます!」
『お久しぶりです。かんぱい。』
「おぉ、美味い!度数は少し高めですね。そしてこのスモーキーな味が、何かいろんなことをかき消してくれますよ。さすがのチョイスです。」
『いいでしょう。日本のウイスキーもここが出来てから人気が高まってきたんですよ。』
「あっ、ママも一緒に乾杯したいけど。」
『すみません。例の…』
「そっか、猫の世話ですね。」
「今日は、来てよかったです。何か吹っ切れました。」
『それは、良かったです。きっと彼女さんも気にされていますよ。』
「うん。な、なんで分かるんですか!フラれたことを…」
『はい。なんとなくね。』
「クリスマスが近いこの時期に、フラれるなんて悲しすぎますよね。」
『ここがあるじゃないですか。この冬は、ここで暖まってください。』
「・・・・。」
ほんとに暖まるBARだ。このお店に通うようになれてよかったと思う。マスターとママの絶妙なバランスがとても癒されるし、元気をもらえる。もっと早く来ればよかったかもしれない。
「もうこんな時間ですね。閉店の12時を過ぎてました。すみません。」とマスターに声をかけた時に、奥の方から”ミャー”とまた小さな鳴き声が聞こえた。
『お迎えが来たようです。これで閉店します。二階に戻るのにまた15分はかかりますからね。』
「マスター。ありがとうございます。暖まりにまた来ます。」