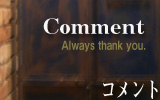「マスター!」とカウンター角の席から声がした。いつもの常連さんがいつもの席で、空になったグラスを鳴らしていた。
『はいはい。何でしょう?』
「お代わりですよ。ハイボール!」
『まだ飲むの!もう1時をまわっているよ。』
「もう1杯だけいいでしょう。」
『分かりましたよ。最後ですよ。明日も仕事でしょ。』と空のグラスを下げ、新しいハイボールをつくって常連さんの前のコースターの上に運んだ。
とその時、扉がゆっくり開き「まだ、いいですか?」と丁寧な声と一緒に着物姿の一人の女性が入って来た。
『どうぞ、まだ大丈夫ですよ。いらっしゃいませ!』と声を返しながら、カウンターの真中の席に案内した。
「ごめんなさいね。こんな格好で・・・。」
『とんでもないです。いつも、お着物で・・・。』
「はい。40年、着物で仕事してますね。」
『素敵ですね。ところで、何にいたしましょうか?』
「私は、昔からバーが好きで、この街にもバーがたくさんありましたね。よく行ってましたよ。フィズを飲みにね。」
『かしこまりました。それではフィズをおつくりしましょう。』
「お任せしますわ。」
『はい。』と返した後、バック棚からバイオレットのリキュールを取り出し、レモンを絞って一緒にカウンターの上に置いた。
シェーカーにリキュールとレモンジュースを入れ、シュガーシロップをバースプーンで加えた。そして、氷を入れて素早くシェイクする。冷しておいたタンブラーに注いで氷を入れ、炭酸を満たしてレモンスライスを飾れば出来上がりだ。
『はい。お待たせいたしました。』と言葉を添えて、女性のコースターの上に静かに運んだ。簡単なカクテルではあるが、少し緊張していた。
「あら、“バイオレットフィズ”ですね。懐かしいわ。」
『お着物の色に合わせてみました。いかがですか?』と話した後、女性はしばらくカクテルを眺めていた。そして、おもむろにグラスを静かに持ち上げ、紅色の口元まで運んだ。
「美味しいわ。昔を思い出すわね。昭和30年代の終わり頃かしら・・・。バーに行けば、フィズかハイボールばっかりでしたわ。」
『僕が生まれた頃ですね・・・。』
「まぁ、まだお若いわね。でも、ここの店はお酒がたくさんあって、天井も高いし、それにこのカウンターの幅が広くて・・・。ホント、昔を思い出す造りですわね。」
『あ、ありがとうございます。まだ若いですけど、あと20年もすれば、もうちょっと味のあるバーの主人になってると思います。』
「身体に気をつけて頑張ってくださいね。」
『はい・・・。』と笑顔で返した。そして、女性は残りのカクテルを静かに飲み干した。そして、紅色の口元がまた動いた。
「今日はね。1杯だけと決めて来たんですよ。だから、これで失礼しますね。」
『ありがとうございます。』
「また、来させて下さいね。あっ、それに、昔、通っていたバーでも、着物の色に合わせてくれたんですよ。紫は好きな色なんです。」
『また、よろしくお願いいたします。』
と外までお見送りをした。そして、カウンターの中に戻り、いつもの常連さんの前に行った。
「ねぇ、マスター。」
『はい。何でしょう?』
「素敵な方でしたね。」
『そうだね。着物姿は、何ともいえない雰囲気があるね。』
「そうそう、マスター!緊張してたでしょ!」
『あたり前ですよ。私が生まれた頃からバーに通ってる方ですよ。粗相がないようにしないとね。』
「そうですよね。昔を思い出しに来られたんでしょう。たぶん…。」
『おぅ、あなたにしては、さえてるじゃないですか!』
「ところでさぁ、フィズってどういう意味なの?」
『あのね、質問はいいけど、閉店時間だけど!』
「じゃぁ、もう一杯お代わりつくって下さいよ!」
『もう、ホントにこれで最後ですよ。』と言って、ハイボールを二杯つくった。
『はい、どうぞ、私もいただきますよ!あなたのおごりで…。』
「わ、分かりましたよ!で、名前の意味は?」
『それはね、ハイボールにも入っているけど、炭酸のガスが立てる“シュッ”という音からきた擬声語だと言われているんですよ。分かるかなぁ…。』
「分かります!」
『ところで、婚カツはどうなったの?』
「えぇ、今度は僕に質問ですか?マスター、酔ってきてるでしょ!」
『まだまだ…。』
「あのう…。閉店時間も過ぎたことだし、マスター、一緒に帰りましょうか!」
『質問に答えなさい!』
「もう…。」