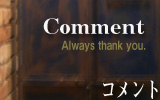予定通りの時間に、扉が開いた。言わずと知れたいつもの常連さんである。
『いらっしゃい!』と声をかけ、ハイボールをつくって角の席へ運んだ。
「マスター。今日は、すぐ帰りますから。」
『そ、そうなの・・・。ところで、誕生会はどうだった?』
「楽しかったよ。でも、プレゼントを渡せなかった・・・。タイミングがなくて・・・。」
『酔っ払って、忘れたとかじゃないの!』と返した時に、また、扉が開く音がした。
『いらっしゃいませ!』と扉の方へ声をかけた。
「こんばんは!」と声を出しながら一組のカップルが入ってきた。
『どうぞ、こちらの方へ』と、真ん中よりの席にご案内し、オシボリを渡し、お二人の前にコースターを置いた。
「マスター!お久しぶりです!」
『ホントですね、4年ぶりですか。』
「もう、そんなになるんだ・・・」と言う女性の方へ向くと、また男性から声がした。
「妻です。一年前に結婚しました。」
『そうですか。あの頃は、学生さんでしたね。』
「はい。大学がこっちで、そこで知り合って・・・。」
『おめでとうございます! ところで、何にしましょうか?』
「えっと。僕は、ウイスキーのロックを、妻には何かカクテルをつくって下さい。」
『かしこまりました。』と返事をして、バック棚を見渡して、まずウイスキーを取り出し、カウンターの上に置いた。それから、ピーチ・リキュールとアプリコット・リキュールとブルーキュラソーを取り出し、同じように並べた。ライムを一個搾り、その並んだボトルの横に置いた。そして、冷しておいたカクテル・グラスにレッドチェリーを一個入れて準備をした。
シェーカーに材料を入れ、氷を加えて、すばやくシェーク。静かな店内に透き通るような金属音響いた。シェーカーのトップを外して砕けた細かい氷とともに薄い緑色の出来たばかりの液体をグラスに注いだ。
『はいどうぞ。お待たせしました。』と言ってカクテルを出し、ご主人には、丸い氷を一個入れたロック・グラスにウイスキーを注いで、静かにコースターの上に運んだ。乾杯の声と一緒に、それぞれグラスを口に運んだ。
「美味しい!それに色がすごくキレイ・・・。」の後、ご主人からも声がした。
「このウイスキーも美味いよ。香りもいい。」
『カクテルは、“フェアリー・テール”と言う名前です。18年ぐらい前に、ある女性のお客様が、その時につくったオリジナル・カクテルに名前を付けてくれたもので、“妖精が出てくるお伽話”と言う意味だそうです。それ以来、当店のメニューにもその名前で載せているんですよ。
ウイスキーは、国産で“白州12年(サントリー・シングルモルト・ウイスキー)”です。』
「かわいい名前だね。」と二人で目を合わせ、すぐにご主人が口を動かした。
「僕の職場は、山の中の自然公園施設なんです。回りには森があって、ホントに妖精が居そうな場所なんですよ。」
『そうですか、羨ましいですね、そういう所で仕事ができて・・・。』
「妻には、少し不便な思いをさせているけど、気に入っているんです。自然に囲まれてて、いつか子供ができたら、いっぱい遊ばせてやりたいと思っています。」
『そのうちに、可愛い“幼生”を授かりますよ。』と答えた後、二人のそばからしばらく放れた。
常連さんのハイボールが空になっていた。お代わりをつくって角の席の前に行き、新しいものと取り替えた。その時、ご主人のグラスの氷が鳴る音が聞こえた。
「マスター!今日はこれで帰ります。美味しいウイスキーとカクテル、ありがとうございました。」
『こちらこそ、ありがとうございました。また、寄って下さい。』
「はい。妻の実家はこっちなので、また、寄ります。」
『そうそう、お出ししたウイスキーも、森の中で育ったものなんですよ。』
「そんな、香りがしてました。」と話しながら、外まで見送った。
店の中に戻り空になった二つのグラスを下げ、洗った後、拭き上げながら常連さんの方へ身体を向けた。
『ところで、さっきの話しの続きだけど・・・。』
「マスターに頼みがあって・・・、このプレゼントのグラスを預かって下さい。ここに一緒に来た時に渡したいから・・・。」
『そう言うことなら、喜んで引き受けましょう。』
「よかった。今日は、そのお願いで来たんです。では、これで・・・。」
『えぇ、もう、帰るの!』
「少し、風邪気味で・・・。」
『今流行のインフルエンザじゃないでしょうね。』
「ち、違いますよ。たぶん・・・。」
『明日、病院に行って検査して下さい。“ようせい”かもよ。』
「僕に、“妖精”は来ないでしょう。」
『その“ようせい”じゃありません。』
「あぁ、そっちね。当りかも・・・。」