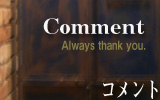最近、何やら新しい感染症がはやり始めている。薬もワクチンもまだ開発されていないために、ロックダウンとはならなくても緊急事態宣言が発令されたりして飲食店は大打撃だ。
まぁ、当店は昔から暇な店なので影響は少ないと思っていたが、いつもの常連さんも気を付けているのか全然顔を出さなくなった。当店も大打撃だ。いったいいつまで続くのだろうか。
こんな状況の中、今日は蒸留家と称し独立して、クラフトジンの蒸留所を立ち上げた方から20時に予約が入っている。そろそろお見えになるころだ。
入口の重たい扉に付いたドアベルの音が「カランカラン」となった。
『こんばんは。今日はすみません。こんな状況の中で…』とオレンジ色のポロシャツを着て、黒いマスクを付けた男性が入ってきた。
「どうぞ、こちらへ。」とカウンターの一番奥の席を案内した。
『いやな感染症が流行ってますね。佐賀も影響が出始めましたね。』
「そうですね。うちは暇なうえに人が動かなくなると、自家消費ばかり増えて大変ですよ。」
と口元に笑みをつくり話したが、私もマスクをしていた。
『初めまして。今日は、やっとできた佐賀初のクラフトジンをお持ちしました。ぜひマスターに飲んでいただきたくて。』
「それはそれは、ありがとうございます。」
現在、国内ではウイスキーの新規蒸留所も増えているが、クラフトジンもそれに劣らず増加している。大手メーカーから、日本酒や焼酎製造業者も、またウイスキー蒸留所も3年で最初のウイスキーが出来るまで、ジンを造るところが多いようだ。そして、つい最近、佐賀にも一人で独立し小さな蒸溜所を立上げて、クラフトジンの製造を開始したという話しを聞いたばかりだった。
『これです。』
「いい感じのボトルですね。ラベルもかわいいし、オレンジ色が効いてますね。」
『オレンジは、オランダの色なんですよ。』と満面の笑みだと分かるマスク顔で、話しが続いた。
『佐賀、特に幕末佐賀藩は、オランダと深い関係があるんです。当時出島を警護していた佐賀藩は、オランダと交流し、その技術をいち早く取り入れたり、蒸気船を輸入して技術を調べ上げて、日本初の蒸気船‟凌風丸“を完成させたんですよ。』
「はい。知ってますよ。維新博でも分かりやすく紹介されていましたね。と、このジンは何か関係があるんですか?」
『実は、会社を立上げて、直ぐにオランダに行ってきました。オランダの蒸留器が使いたくて...』
「オランダの技術を使うということですね。」
『はい。』
「なるほど、佐賀初クラフトジンは、幕末佐賀藩のストーリーと被るということですね。」
『そ、そうなんです。』と少し声が大きくなり、マスクの上の目はキラキラ輝いていた。
『一人で仕込から蒸留まで何でもやります。おそらく日本一小さい蒸溜所だと思います。』
「ジンと一緒に物語もつくっていくということですね。素晴らしいと思います。」
『ありがとうございます。で、出来たばかりのジンをちょっと飲んでみてください。』
棚から、グラスを2個取りだしてボトルを握りしめ、ゆっくり注ぎ分けた。真珠色に輝く液体がグラスへと落ちていく。
「香りはおだやかですね。おぉ、飲むとシッカリとジン特有のジュニパーベリーの香りと味が感じられますね。後口は、甘さというかなんかうま味が感じられますね。」
『そうなんです。一般的なクラフトジンは辛口なのですが、このジンは甘さがありそれがうま味として一つの特徴となっています。』
「確かに。」
『さっきの話ですが。佐賀藩がつくり上げた蒸気船には、オランダの技術と佐賀独自の技術も入っているんですよ。』
「というと、オランダの蒸留器と造り手の技術が融合していると…」
『はい。そうなんですが、もう一つ佐賀の素晴らしい技術が入っているんです。』
「このうま味ですか。ずっと気になっているんですよ。不思議と飲み飽きないジンだなぁと。」
と話したあと、さらに目がキラキラと輝いたように感じた。
『やはり、マスターはすごいですね。気付いてくれましたね。嬉しいです。』
「もう一つの答えは日本酒ですか!」
『その通りです。佐賀は日本酒文化が定着していて素晴らしい蔵元がたくさんあります。その蔵元さんにお願いして、純米吟醸酒でベース用のスピリッツを造ってもらい、それにボタニカルを漬け込んで、オランダ製の蒸留器で再蒸留し佐賀の名水で割水して、アルコール度数45度の商品にしています。』
「佐賀がいっぱい詰まったジンですね。それに想いもいっぱい詰まってますね。」
『ありがとうございます。佐賀が好きなんですよ。』
「私もです。」
『このジンを基本に、面白いものを造っていきたいと思っています。ただ、ジンというとキリっとした爽やかな辛口というイメージが一般的なので、このジンが浸透して行くには少し時間がかかりそうです。』
「私も、協力しますよ。うま味のある飲み飽きないジン、カクテルにしなくてもウイスキーと同じように楽しめるジンだと思います。」
『今日は、早い時間からすみませんでした。この1本は置いていきますので、ぜひお客様に試飲していただくとありがたいです。』
「かしこまりました。一人いるんですよ。」
『ぜひ、その方にお勧めしてください。では、これで失礼します。今後ともよろしくお願いします。』
と帰られ、扉のドアベルの音が小さくなっていった。
いつもの常連さんはハイボールしか飲まないし、このジンが分かるかなぁ。と頭の中で考えていた時、またドアベルの音が鳴った。
『やぁ、こんばんは!』
「おぉ、いらっしゃい。今、あなたの事を考えていたところですよ。」
『フラれて、ハイボールしか飲まない変な客だってことでしょ。』
「あ、た、り。」
変な感染症が広まってきてから、初のご来店であるいつもの常連さんだ。いつもの入口に近いカウンターの隅にマスクを付けたままで腰を下ろした。
「手指の消毒もお願いしますよ。」
『ちゃんと入口でしましたよ。』
と平常のお店では言わない言葉を、最近は挨拶のように言うようになってしまった。
「いつも、いいタイミングでご来店しますね。」
『というと、何か新しいウイスキーが入ったということですね。』
「ちがいます。ウイスキーじゃないですよ。」
と会話をしながら、佐賀初のクラフトジンをストレートで、いつもの常連さんのコースターの上に運んだ。
「どうぞ。」
『ス、ストレートですか!しかも透明なヤツじゃないですか。僕の体の中まで消毒しろと言ってるんですか。』
「まぁ、飲んでごらんよ。」
『おぉ、ジンですか?』
「見直しましたよ。これが分かるとは。」
『でも、少し甘いよね。お米のうま味みたいな...』
「な、なんとそこまで分かるとは!これはね、最近発売された‟スティルダムジン・スタンダード“という佐賀初のクラフトジンなんですよ。」
『オレンジ色に、昇開橋をデザインしたかわいいラベルですね。』
「このジンはね、小城の蔵元の純米吟醸酒が使われていて、昇開橋の近くに新しく出来た蒸溜所で造られているんですよ。」
『いいね。マスター、この味好きです。今度からこれでハイボールを造ってくださいよ!』
「は、はい。ソーダ割りね。それもいいかもね。」
『なんか、僕も変われそうな気がしてきました。今までマスターから無理やり飲まされていたハイボールから、このジンに変えます。そして、新しい彼女を見つける。いや見つかるような気がしてきましたよ。』
「このジンで、見つかるかな?」
『見つけますよ。彼女を、素敵な佐賀美人(ジン)を!』
「ちょっと、ダジャレ!今のこの時期、大声を出さないでください。他にお客さんがいないからいいけど。」
『はいはい、ちゃんとマスクしてるからいいでしょ。』
「ダメです。」