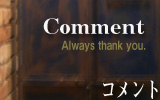「いらっしゃいませ。明けましておめでとうございます。」
2005年になって1週間が過ぎ、正月の慌しさは、もうどこにも残っていない。普通の時間が流れ、お客様を迎える挨拶だけが、新しい年になったのだと感じさせてくれる。
『マスター、大晦日のカウントダウンの時に、僕も居たよ!新しい年になって2度目の来店ですよ!』
「そうだったね。条件反射みたいなもので、言ってしまうんですよ。」
「ところで、いつもので・・・?」 この常連さんとも5年めのお付き合いである。
毎回登場してもらってるので、おわかりかと思いますが、カウンター右隅のいつもの席、いつも最初は“アードベッグ10年”のストレートである。
『マスター!僕はいつも10年物を飲んでいるけど、ウイスキーにはいろんな熟成年数のものがあるよね。長いものでは60年物があると聞いたことがあるんだけど?』
「たまには、自分の飲んでるものをじっくり眺めて飲むと、そう言う質問が出てくるもんですよ!」
『答えて下さいよ!』
「ありますよ。私が知る限りでは、ベン・ネビス62年というのが一番長いかな・・・。有名なのは、マッカランの60年物ですね。バブルの頃は200万円を超えていたから、凄いですよね。」
『熟成が長くなると値段も高くなるんだ・・・。』
「そうだね。単純に考えても、樽の中の原酒が年を重ねるごとに、量が減って行くんですよ。年間約2%から3%が消えて行くと言われていますね。」
『なるほど。量が減るということは、瓶詰めできる本数も少なくなるから高くなるんだ!』
「まぁ、そう言うことですね。で、その熟成中に消えた分を“天使の取り分”と言うんですよ。知ってました?」
『なりたい!天使に!アードベッグの熟成庫の天使に・・・』
「私も同じです。」
『マスター。もう1杯同じのを!』
「はい!かしこまりました.。」と10年物を注いだグラスを常連さんの前に差し出した。と同時にドアが開き、1年ぶりのお客様が入って来られた。
「あっ、いらっしゃいませ!里帰りですか?明けましておめでとうございます。」
『明日、東京に戻るので、マスターの顔を見ないとね・・・』
「ありがとうございます。」 そのお客様は、カウンター左端の席に座られた。
『マスター。“ポートエレン”あるかな?』
「たしか・・・、1本だけあったような・・・。はっ、はい。ありました。シルバーシールのポートエレン1980です。あと1杯分ぐらいしか残っておりませんが?」
『それでいいよ。』
「はい。かしこまりました。」
『このモルトも、熟成庫には樽がほとんどないらしいね。』
「よくご存知で・・・。1983年に蒸留所が閉鎖されてしまい、その後に瓶詰めされた商品もなくなれば、もう飲めなくなりますね・・・」
『モルトファンも残念だね。それと、“天使”もかわいそうだ・・・』
「天使ですか?」
『熟成庫に住む、その・・・』
「エンジェルズ・シェアですね。天使の取り分がなくなってしまうからですか?」
『そういうこと!マスター、ありがとう!貴重なものを飲ませていただいて。また1年後に顔を見に来るとするよ。』
「お待ち申し上げております。」とドアが閉まるまで頭を下げていた。
『ねぇ、マスター!グラスが空だけど・・・』
「あっ、すいませんね。」
『いまの人、ポートエレンが好きなんだ!それと天使にまで気を使うとこがいいね。マスター、そのポートエレン、少し残ってるね。それ!飲みたい!』
「よく見てましたね。だめです!この少し残った分は“店主(天使?)の取り分”なんだから!」
『なにそれ・・・』
「たまには、店主にも気を使ってくださいな!」
2005年になって1週間が過ぎ、正月の慌しさは、もうどこにも残っていない。普通の時間が流れ、お客様を迎える挨拶だけが、新しい年になったのだと感じさせてくれる。
『マスター、大晦日のカウントダウンの時に、僕も居たよ!新しい年になって2度目の来店ですよ!』
「そうだったね。条件反射みたいなもので、言ってしまうんですよ。」
「ところで、いつもので・・・?」 この常連さんとも5年めのお付き合いである。
毎回登場してもらってるので、おわかりかと思いますが、カウンター右隅のいつもの席、いつも最初は“アードベッグ10年”のストレートである。
『マスター!僕はいつも10年物を飲んでいるけど、ウイスキーにはいろんな熟成年数のものがあるよね。長いものでは60年物があると聞いたことがあるんだけど?』
「たまには、自分の飲んでるものをじっくり眺めて飲むと、そう言う質問が出てくるもんですよ!」
『答えて下さいよ!』
「ありますよ。私が知る限りでは、ベン・ネビス62年というのが一番長いかな・・・。有名なのは、マッカランの60年物ですね。バブルの頃は200万円を超えていたから、凄いですよね。」
『熟成が長くなると値段も高くなるんだ・・・。』
「そうだね。単純に考えても、樽の中の原酒が年を重ねるごとに、量が減って行くんですよ。年間約2%から3%が消えて行くと言われていますね。」
『なるほど。量が減るということは、瓶詰めできる本数も少なくなるから高くなるんだ!』
「まぁ、そう言うことですね。で、その熟成中に消えた分を“天使の取り分”と言うんですよ。知ってました?」
『なりたい!天使に!アードベッグの熟成庫の天使に・・・』
「私も同じです。」
『マスター。もう1杯同じのを!』
「はい!かしこまりました.。」と10年物を注いだグラスを常連さんの前に差し出した。と同時にドアが開き、1年ぶりのお客様が入って来られた。
「あっ、いらっしゃいませ!里帰りですか?明けましておめでとうございます。」
『明日、東京に戻るので、マスターの顔を見ないとね・・・』
「ありがとうございます。」 そのお客様は、カウンター左端の席に座られた。
『マスター。“ポートエレン”あるかな?』
「たしか・・・、1本だけあったような・・・。はっ、はい。ありました。シルバーシールのポートエレン1980です。あと1杯分ぐらいしか残っておりませんが?」
『それでいいよ。』
「はい。かしこまりました。」
『このモルトも、熟成庫には樽がほとんどないらしいね。』
「よくご存知で・・・。1983年に蒸留所が閉鎖されてしまい、その後に瓶詰めされた商品もなくなれば、もう飲めなくなりますね・・・」
『モルトファンも残念だね。それと、“天使”もかわいそうだ・・・』
「天使ですか?」
『熟成庫に住む、その・・・』
「エンジェルズ・シェアですね。天使の取り分がなくなってしまうからですか?」
『そういうこと!マスター、ありがとう!貴重なものを飲ませていただいて。また1年後に顔を見に来るとするよ。』
「お待ち申し上げております。」とドアが閉まるまで頭を下げていた。
『ねぇ、マスター!グラスが空だけど・・・』
「あっ、すいませんね。」
『いまの人、ポートエレンが好きなんだ!それと天使にまで気を使うとこがいいね。マスター、そのポートエレン、少し残ってるね。それ!飲みたい!』
「よく見てましたね。だめです!この少し残った分は“店主(天使?)の取り分”なんだから!」
『なにそれ・・・』
「たまには、店主にも気を使ってくださいな!」