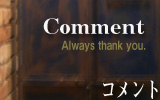今年は寒い日が多いような気がする。3月の半ば、春一番も吹いて暖かくなってもよさそうなのに、真冬並みの寒さである。
『マスター!こんなに寒いと他にお客さんは来ないんじゃないの!』といつもの常連さんがいつもの席でアードベッグ10年のストレートを一口飲んで問いかけてきた。
「そう、こんなに寒い日は、あなたぐらいですよ!飲みに出るのは!」
『悪かったねぇ…。』とつぶやいた時に、「キィッ」とドアの開く音が…。
この場所に移転してもうすぐ7年になる。
分厚い木のドアも重さで歪み、きしむ音がしだした。
「いらっしゃいませ」珍しく女性が一人である。
どうぞ、こちらの方へと、常連さんとは反対のカウンター角の席へ座っていただいた。
女性一人というのは、あまり慣れてないせいか、ちょっと緊張してしまう。
オシボリをお出しし、その女性の前にコースターを置いた。
『マスター。憶えてますか?』の声に、「えっ!」と返して真剣な目で顔に視点を合わせた。「あぁ…。A子ちゃん?」 少し顔が細くなったけど、間違いなくA子ちゃんである。
『よかった!憶えてくれていて…。』
彼女は、10年ほど前に高校の同級生と結婚して佐賀を離れていた。もっと逆上れば、その当時同じ会社の上司とよく一緒に飲みに来ていた。まだ店を移転する前のことだが…。
私もまだ独身だった頃である。彼女は、20代半ばだった。感じのいい女性で、カウンター越しではあるが、密かに好意を寄せていたものだ。
当時は、彼女が先に来て、上司を待つことが多かった。その上司を待つ30分ほどが、私にとって最高の時間となっていたのである。
「佐賀に帰ってきたんだ?」
『そうじゃなくて、実は父が亡くなって・・・、昨日が四十九日だったの、今日まで佐賀にいて明日帰ることにしたから・・・。それよりも・・・。』
「それよりも?どうしたんですか?」
『あの頃、ずいぶんお世話になったな・・・、なんて思って・・・。』
「そんなにお世話したかな?」
『マスターのお店のお陰で、いい思い出をつくることができたしね。あら、ごめんなさい!オーダーもしないで話しに夢中になってしまって、何かカクテルをもらおうかな?』
「ハイ、かしこまりました。とっておきのカクテルをお創りしましょう。」
佐賀には、“さがほのか”という美味しいイチゴがある。ちょうどこの時期が旬で、それを使ってカクテルを作ることにした。
「どうぞ!さがほのかを使ったカクテルです。」
『綺麗な色に、イチゴのいい香り・・・。』『お・い・し・い!』
「美味しいでしょう!」
ラムをベースにイチゴを潰して加え、フランボァーズとレモンを少し入れてシェイクしたものである。店のオリジナルに“TOMADOI(戸惑い)”というカクテルがある。
それに“さがほのか”を潰して加えてアレンジしたものだ。
『マスター!このカクテルの名前は?』
「な!名前ですか?んー。ほのかな想い・・・、かな?」
『“ほのかな想い”かぁ、いい名前・・・。』
あの頃の彼女に対するカウンター越しの想いをカクテルにしたなんて、とても口には出すことは出来ない。
『マスター。ありがとう。気を使ってくれて・・・。』
「そ・そんな、大した気は使ってないですよ。」と言ったところで、常連さんの方へ目を向けると、グラスは空になっていた。
『マスター!とっくにグラスは空になっていたのに・・・。気付いてくれないんだから!今日は、なんだかマスターが遠く感じるなー。』
「どうも、すいません。おかわりしましょうか?」
『僕は、こんなにこの店に通っているのに、まぁ、ここに移転してからの客だけど・・・。とっておきのカクテルなんか出してもらったことがないよね。僕も、イチゴ好きなんだ・・・。』
「わ・分かりましたよ!確か、ジンも好きですよね。」
今日は、自分でも店の空気が違うと感じていた。こういう日に常連さんと、昔、ほのかに想いを寄せていた女性と二人だけというのは、どうも仕事しにくいものである。
「はい、どうぞ!」と常連さんもイチゴを使ったカクテルをお出しした。カクテルグラスに“さがほのか”を一粒入れて、よく冷やしたジンを注ぎ、ほんのちょっとトニックウォーターを加えたものである。
『マスター!イチゴを丸ごと入れたカクテルなんて見たことがないよ!これって、手抜きなんじゃないの…。』
「まぁ、そう言わずに飲んで下さい!中のイチゴはタテに4つに切れてるから、一切れずつ食べながら飲むとうまいよ!」
『本当かよ!』と言って、イチゴを一切れ口に放り込み、食べながらジンをすする音がした。
『ほぉ…。うまいじゃないこれ!』
「でしょう!」
『イチゴとジンって合うんだね。』
「“さがほのか”だから合うんですよ!適度な酸味があるからいいんでしょうね。」
『ところで、名前は?』
「名前ですか!“いちごいちえ”と言うのはどぉ?」
『“一期一会”!』
「いえいえ、“いちご一絵”です。」
『ん…。まったく親父ギャグじゃないですか!』
「そう言わずに、美味しいでしょ!」
『確かに!』と常連さんが返した時に、「マスター!」とキレイな声がした。
「すみません!ほったらかしにしてたわけじゃないんですよ。」と返事をし、彼女の前へ条件反射のごとく動いた。
『最後に、もう一杯だけ飲ませて下さい。ほのかなあの頃に浸りすぎたみたい・・・。』
「そうですか。で、何にしましょう?」
『X.Y.Z(エックス・ワイ・ジィ)をつくってくれますか?』
「・・・。かしこまりました。」
このカクテルは、ラムにコアントローとレモンジュースを加えてシェイクするものだ。その名前から究極のカクテルと言われるもので、彼(彼女の上司)がよく飲んでいたものである。彼にとっては究極の女性だったに違いない。
しかし、彼には、妻も子供もいたのである。お互いの許される時間をBARで一緒に過ごすことが二人にとっての唯一共有できる時間であり、思い出を作るひと時となっていた。
私のほのかな想いなど入る隙間などなかったし、彼女が気付くはずもなかったのだ。
「はい、どうぞ。」とさっきまで“ほのかな想い”が乗っていたコースターの上にそっと差し出した。
『マスター。ありがとう。』と言った後に一口飲み、数秒の間をおいて『こういう味だったんですね。』とつぶやいた。
「いつも、これを飲んでらっしゃいましたね。」と私が言い足しあと、「X.Y.Zの名前から“究極の”という意味があるんですよ。」と加えた。
『そうだったんですね・・・。』しばらく沈黙が続き、常連さんの何かブツブツ言う声だけが聞こえていた。
『でも、これでよかったんですよね。』
「はい、私もそう思います。」
『マスター。今日は、来てよかった。』
「ありがとうございます。」
彼女をドアの外まで見送って、店の中に戻った。
『マスター!なんか空気が重かったけど…。』と常連さんの声がした。
『ねぇ、僕にも“X.Y.Z”を飲ませてよ!僕にとっての究極は、この店にいつも一人でいることかな!』
「そうですか?そうそう、言い忘れていたけど、このカクテルには、もう一つ意味があるんですよ。“これで最後”という意味がね…。」
『じゃ、さっきの彼女のカクテルは・・・。』
「相変わらず、ニブイネ。思い出は、今日で終わりにしたかったんですよ。」
「ところで、そのカクテルで“最後”にして下さい!今日は、早閉まいするから!」
『そんなぁ!』
「私は、よその店で“X.Y.Z”を飲んで帰ります!」
『僕も、付き合います。』
「・・・。一人にさせて下さい!」
『マスター!こんなに寒いと他にお客さんは来ないんじゃないの!』といつもの常連さんがいつもの席でアードベッグ10年のストレートを一口飲んで問いかけてきた。
「そう、こんなに寒い日は、あなたぐらいですよ!飲みに出るのは!」
『悪かったねぇ…。』とつぶやいた時に、「キィッ」とドアの開く音が…。
この場所に移転してもうすぐ7年になる。
分厚い木のドアも重さで歪み、きしむ音がしだした。
「いらっしゃいませ」珍しく女性が一人である。
どうぞ、こちらの方へと、常連さんとは反対のカウンター角の席へ座っていただいた。
女性一人というのは、あまり慣れてないせいか、ちょっと緊張してしまう。
オシボリをお出しし、その女性の前にコースターを置いた。
『マスター。憶えてますか?』の声に、「えっ!」と返して真剣な目で顔に視点を合わせた。「あぁ…。A子ちゃん?」 少し顔が細くなったけど、間違いなくA子ちゃんである。
『よかった!憶えてくれていて…。』
彼女は、10年ほど前に高校の同級生と結婚して佐賀を離れていた。もっと逆上れば、その当時同じ会社の上司とよく一緒に飲みに来ていた。まだ店を移転する前のことだが…。
私もまだ独身だった頃である。彼女は、20代半ばだった。感じのいい女性で、カウンター越しではあるが、密かに好意を寄せていたものだ。
当時は、彼女が先に来て、上司を待つことが多かった。その上司を待つ30分ほどが、私にとって最高の時間となっていたのである。
「佐賀に帰ってきたんだ?」
『そうじゃなくて、実は父が亡くなって・・・、昨日が四十九日だったの、今日まで佐賀にいて明日帰ることにしたから・・・。それよりも・・・。』
「それよりも?どうしたんですか?」
『あの頃、ずいぶんお世話になったな・・・、なんて思って・・・。』
「そんなにお世話したかな?」
『マスターのお店のお陰で、いい思い出をつくることができたしね。あら、ごめんなさい!オーダーもしないで話しに夢中になってしまって、何かカクテルをもらおうかな?』
「ハイ、かしこまりました。とっておきのカクテルをお創りしましょう。」
佐賀には、“さがほのか”という美味しいイチゴがある。ちょうどこの時期が旬で、それを使ってカクテルを作ることにした。
「どうぞ!さがほのかを使ったカクテルです。」
『綺麗な色に、イチゴのいい香り・・・。』『お・い・し・い!』
「美味しいでしょう!」
ラムをベースにイチゴを潰して加え、フランボァーズとレモンを少し入れてシェイクしたものである。店のオリジナルに“TOMADOI(戸惑い)”というカクテルがある。
それに“さがほのか”を潰して加えてアレンジしたものだ。
『マスター!このカクテルの名前は?』
「な!名前ですか?んー。ほのかな想い・・・、かな?」
『“ほのかな想い”かぁ、いい名前・・・。』
あの頃の彼女に対するカウンター越しの想いをカクテルにしたなんて、とても口には出すことは出来ない。
『マスター。ありがとう。気を使ってくれて・・・。』
「そ・そんな、大した気は使ってないですよ。」と言ったところで、常連さんの方へ目を向けると、グラスは空になっていた。
『マスター!とっくにグラスは空になっていたのに・・・。気付いてくれないんだから!今日は、なんだかマスターが遠く感じるなー。』
「どうも、すいません。おかわりしましょうか?」
『僕は、こんなにこの店に通っているのに、まぁ、ここに移転してからの客だけど・・・。とっておきのカクテルなんか出してもらったことがないよね。僕も、イチゴ好きなんだ・・・。』
「わ・分かりましたよ!確か、ジンも好きですよね。」
今日は、自分でも店の空気が違うと感じていた。こういう日に常連さんと、昔、ほのかに想いを寄せていた女性と二人だけというのは、どうも仕事しにくいものである。
「はい、どうぞ!」と常連さんもイチゴを使ったカクテルをお出しした。カクテルグラスに“さがほのか”を一粒入れて、よく冷やしたジンを注ぎ、ほんのちょっとトニックウォーターを加えたものである。
『マスター!イチゴを丸ごと入れたカクテルなんて見たことがないよ!これって、手抜きなんじゃないの…。』
「まぁ、そう言わずに飲んで下さい!中のイチゴはタテに4つに切れてるから、一切れずつ食べながら飲むとうまいよ!」
『本当かよ!』と言って、イチゴを一切れ口に放り込み、食べながらジンをすする音がした。
『ほぉ…。うまいじゃないこれ!』
「でしょう!」
『イチゴとジンって合うんだね。』
「“さがほのか”だから合うんですよ!適度な酸味があるからいいんでしょうね。」
『ところで、名前は?』
「名前ですか!“いちごいちえ”と言うのはどぉ?」
『“一期一会”!』
「いえいえ、“いちご一絵”です。」
『ん…。まったく親父ギャグじゃないですか!』
「そう言わずに、美味しいでしょ!」
『確かに!』と常連さんが返した時に、「マスター!」とキレイな声がした。
「すみません!ほったらかしにしてたわけじゃないんですよ。」と返事をし、彼女の前へ条件反射のごとく動いた。
『最後に、もう一杯だけ飲ませて下さい。ほのかなあの頃に浸りすぎたみたい・・・。』
「そうですか。で、何にしましょう?」
『X.Y.Z(エックス・ワイ・ジィ)をつくってくれますか?』
「・・・。かしこまりました。」
このカクテルは、ラムにコアントローとレモンジュースを加えてシェイクするものだ。その名前から究極のカクテルと言われるもので、彼(彼女の上司)がよく飲んでいたものである。彼にとっては究極の女性だったに違いない。
しかし、彼には、妻も子供もいたのである。お互いの許される時間をBARで一緒に過ごすことが二人にとっての唯一共有できる時間であり、思い出を作るひと時となっていた。
私のほのかな想いなど入る隙間などなかったし、彼女が気付くはずもなかったのだ。
「はい、どうぞ。」とさっきまで“ほのかな想い”が乗っていたコースターの上にそっと差し出した。
『マスター。ありがとう。』と言った後に一口飲み、数秒の間をおいて『こういう味だったんですね。』とつぶやいた。
「いつも、これを飲んでらっしゃいましたね。」と私が言い足しあと、「X.Y.Zの名前から“究極の”という意味があるんですよ。」と加えた。
『そうだったんですね・・・。』しばらく沈黙が続き、常連さんの何かブツブツ言う声だけが聞こえていた。
『でも、これでよかったんですよね。』
「はい、私もそう思います。」
『マスター。今日は、来てよかった。』
「ありがとうございます。」
彼女をドアの外まで見送って、店の中に戻った。
『マスター!なんか空気が重かったけど…。』と常連さんの声がした。
『ねぇ、僕にも“X.Y.Z”を飲ませてよ!僕にとっての究極は、この店にいつも一人でいることかな!』
「そうですか?そうそう、言い忘れていたけど、このカクテルには、もう一つ意味があるんですよ。“これで最後”という意味がね…。」
『じゃ、さっきの彼女のカクテルは・・・。』
「相変わらず、ニブイネ。思い出は、今日で終わりにしたかったんですよ。」
「ところで、そのカクテルで“最後”にして下さい!今日は、早閉まいするから!」
『そんなぁ!』
「私は、よその店で“X.Y.Z”を飲んで帰ります!」
『僕も、付き合います。』
「・・・。一人にさせて下さい!」