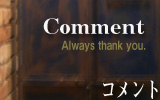吉野ヶ里町で、1989年2月、大規模な環濠集落跡が見つかった。V字型に深く掘られた環濠跡は2.5キロメートルにもおよぶもので、弥生時代後期には外壕と内壕の二重の環濠ができ、敵の侵入を防ぐために木柵、土塁、逆茂木が施されていた。その環濠の中には建物の遺構がいくつも発見されている。竪穴住居、高床住居、祭祀が行われる祭殿や青銅器製造の跡も発見された。
その当時、邪馬台国に関する遺跡ではないかとも言われて、九州王朝説論争にまた火が付いたのである。この物語は、吉野ヶ里遺跡が発見された頃の不思議な物語である。
ある日の夕方、吉野ヶ里の小高い丘で元気よく遊んでいる中学生の子供達がいた。その中の一人の少年が、何かにつまずいて転んで足を怪我してしまう。
倒れた拍子に身をかばおうと、咄嗟に地面に手をつき、なにかを無意識に握りしめていた。
「おい、大丈夫か?」と友達の一人が声をかけた。
「大丈夫!」と返事はしたものの右足の膝を怪我してGパンに血が滲んでいた。
その返事を聞いて、友達は少年にまた声をかけた。
「そう言えば、お前の姉ちゃんも怪我してたなぁ…。姉弟おそろいで、仲の良い事。」
その少年には三つ上の姉がいて、この下の道を自転車で通っている時に、転び足を骨折する大怪我をしていた。
少年は、怪我をしたため、友達たちと早めに別れて家に帰った。服を着替え、怪我した膝にカットバンを貼り、脱いだ服を片付けようとGパンを取った時にポケットに何か入っているのに気づいた。それは、倒れた時に咄嗟に握りしめた物だった。青いガラス製の管のような物で片方が割れていた。
夕飯とお風呂を済ませて、傷口に薬をぬり、明日の宿題を片付けてベットに入った。しばらくして、その足の傷が、痛みだしうなされてしまう。そして、いつの間にか眠ってしまった。
少年は深い眠りに落ちて行くその間に、何か声が聞こえて来た。
「ねぇ、助けて下さい。お願いです…」と言う女性の声に、少年はゆっくり目を開けた。そこは、学校の教科書によく載っている弥生時代のもののような櫓の中だった。そして、まわりの景色もそこに居る人達の身につけている服も教科書の中の絵にあるようなものだった。
「おぉ…、目が覚めたか!タケル(武)!」と老婆が声を上げた。
「タケル? 」と小さくつぶやき声の方を向いた。そこには、一人の老婆と数人の大人達がいて、その櫓の中の一段高くなったところに、さっきの声の主だろう女性がいた。少年がいるところからは、その女性の顔はよく見えなかった。
女性は、ヒムカ(日向花)と言い、タケルは弟である。老婆は、不思議な力を持つ祈祷師で、何やら体じゅうを装飾し、両腕には大きな貝殻を繰る抜いた腕輪みたいなものが幾つも付けてあり、村人からは、神様みたいに崇められていた。
そして、ヒムカとタケルのおばあちゃんでもあるのだ。父と母は、この村を最初に築き上げたが、いく度となく起こる戦いですでに亡くなっていた。
タケルが目が覚めたのは、老婆がお祈りと呪文のような言葉をかけたからだっ
た。
「ここは何処ですか?あなた達は…?」と少年は声を出した。
「まだ、戦いの後で、正気に戻ってないようじゃ」と老婆がつぶやき、大人の一人がその後に話しかけてきた。
「タケル様、先ほどは勇者のような戦いでしたよ。」
大人達は、先ほどの戦いの話をしている。どうやらタケルは、大人達と一緒に戦ったらしく、姉のヒムカを守りその時に倒れて気を失い、老婆の何やら不思議な力で助かったと皆んなは、思っているようだ。
「ぼ、僕は、戦ったの?」
そう、小さい声でつぶやいた。
ヒムカや、老婆を含め100人程が暮らす村は、とても恵まれた場所にある。北には豊富な農作物が取れる畑がつくられ、真ん中の小高い丘には、竪穴式住居の集落がある。南に下ると広い海があり、海産物も取れる。
両親が築き上げたこの村の恵まれた立地は、他の勢力を強めている部族から狙われていて、村人達は、いつかは大きな戦いがおこり、この場所が奪われてしまうのではないかと恐れていた。そんな話しを聞き時間が経つにつれて、少年は夢を見ているのではなく、この村に生まれ育ってきたのだと思うようになっていった。また、ヒムカは、日増しに能力を高めて行き、いつしか村をまとめるようになって行った。そして、老婆は、ヒムカをこの村の王に任命した。
それから数日が経ち、ヒムカは自分で作った青い管玉の首飾りを、老婆に力を入れてもらい、弟であるタケルに渡すように頼んだ。老婆は祀られていた一本の青銅製の剣とその青い管玉の首飾りを渡した。それから、老婆は、タケルに言った。
「この剣を持つ者は、勇者であり、青い管玉を身に付けた者は、この村の王、ヒムカを最後まで守ることを誓わなければならない。」
タケルは、右手に剣を持ち、管玉の飾りを、自分の首に付けて、老婆に声を返した。
「はい!この村と王を守ってみせます。」
王ヒムカは、村を守るために男たちを集め、この村の周りに二重の環濠を造り、その周りに柵を巡らせることと、丘の一番高いところに、物見櫓を作るよう指示を出した。タケルは、ほかの男達を集め、戦い方と武器作りの指示をだし、一緒に準備を進めた。
そして、その戦いの日がやって来た。
今までとは違う数の敵の兵士が近づいて来るのが物見櫓から見ることが出来た。
「て、敵がきたぞ!」と櫓の方から大きな声が聞こえた。
「タケル、準備はいいか?」と老婆がすぐに声をかけてきた。
「はい、この剣と管玉の誓いで、力が湧いてきました。必ず守ってみせます。」
敵は、二重に掘られた環濠と柵により中には入って来れない。一箇所だけ小さい丘に通じる路があるが、敵がそこを通ることを予測して罠を仕掛けてある。深く掘られた落とし穴の底には、木の枝で作った槍を何本も立ててある。この落とし穴は大成功だった。そして、その罠に落ちなかった敵とタケルの最後の戦いが始まった。村を守るため、その村をまとめ築いてきたヒムカいや姉を守るために…。
その姉から貰った青い管玉の力なのか、自分には到底無いはずの不思議な力が備わっていた。
タケルは、敵を丘の上まで誘い、漲る力で敵を次々と倒していった。
「あと一人だ、いくぞ!」と自分に声をかけ、向かっていた。
激しい戦いは終わり、ヒムカの村は守られた。何人もの怪我をした男たちが、物見櫓の下に集まり、老婆が祈りと呪文をかけている。そして、その櫓の真ん中には、ヒムカが立っていた。ヒムカは、勇敢に戦った男たちをねぎらい、それを支えた女たちに優しく声をかけていた。しばらくして、ヒムカも老婆も村人も、弟のタケルがいないことに気付いた。
タケルは、小高い丘の側で倒れていた。最後の敵と相打ちになったのである。倒れている側には、青銅の剣と青い管玉が首からはずれ繋いであった紐も切れてバラバラに落ちていた。
ヒムカは、タケルの顔を見て、涙を流しながら「しっかりして!お願い目を開けて!」と何度も何度も体を揺さぶりながら声をかけ続けた。王になって、こんなに近くで弟の顔を見るのは、初めてだった。
そして、タケルは、ゆっくり目を開けた。
そこには、さっきまでの風景ではなく、いつもと変わらない自分の部屋の中だった。目の前には、母親の顔があった。怖い夢を見てうなされもがいていたらしく、その声と音に心配しておこしにきてくれたのだった。
少年は、そこで夢を見ていたことに気づいた。あまりにもリアルな不思議な夢だったけど、その夢のことは、親にも友達にも話さなかった。
そして、一週間が経ち土曜日の昼過ぎ、いつもの友達がまた遊びに行こうとやってきた。この前のあの丘のところで遊ぶことになり、皆んなで向かった。
しかし、そこにはもう入ることが出来なかった。立入禁止の看板が立っていて、柵で囲まれていた。そこからは、二つの甕棺が発掘され。一つは、女性だろうと思われる人骨が埋葬され、勾玉や鏡などの副葬品と腕には貝殻をくり抜いた腕輪をしていた。もう一つには、たくさんの青いガラス製の管玉と剣だけが埋葬されていて、人の骨は入っていなかった。
もともと埋蔵文化財があると思われていた場所だったのである。
次の日の新聞に大きく記事が載っていた。邪馬台国は九州にあった?という見出しと甕棺から青銅製の剣と青いガラス製の管玉が12個出土したが、その中には埋葬された人骨が入っていなかった。それが謎であるということと、剣には戦った跡が残っていたらしく、管玉は戦った勇者が身に付けていたはずだが、数がおかしいと書かれていた。普通は奇数で、勇者の階級によって、7、9、11、13個なのだと考古学者の持論も書かれていた。
少年は、その記事と一緒に乗っていた写真を見て、ある物を思い出した。そして、慌てて自分の部屋に戻り、机の引き出しを開けた。そこには、前に遊んで怪我した時に咄嗟に握りしめていた物が入っていた。
それは、割れてはいたが、あの発掘された青い管玉と同じ物だった。
そして、またそれを握りしめた。すると一週間程前に見た夢が頭の中を駆けめぐりはじめ、胸が高鳴って行くのを感じ、思わず「うぉぉぉ!」と叫んでしまった。
その声が聞こえたのか、母親が部屋に入ってきた。「どうしたの!そんなに大声を出して!」と聞かれ、「いや、な、何でもない…」と冷静に答えた。
そして、母親は、入院している姉の話を始めた。
「熱も下がりだいぶ良くなったみたいだから、お見舞いにでも行ったら…。一度も顔を出してないでしょ。」
「分かったよ。行くよ。気になる事もあるし…。」
「気になるんだったら、早く行けばいいのに…。」と、母親との会話を終えて、姉が入院している病院へ向かった。
姉は、ひと月ほど前に、あの丘のそばで怪我をして足を骨折した。怪我したところからバイキンが入ったらしく、高熱が出たのでそのまま入院することになってしまった。でも今では、骨もつながり、熱も下がったので、退院も近いようだ。
病院に着き、姉の病室へ向かった。個室のドアを開け中に入った。姉は、ベッドの上で身体を起こして新聞を見ていた。
「姉ちゃん…」と声をかけた。
「遅いなぁ、来るのが…もうすぐ退院するのに…」と、元気な姉の声に少しホッとした。
「ゴメン。あっ、これ…」とポケットに入れていたあの青い管玉を取り出し、夢の話しをしようと思った。
「僕の宝物にしょうと思ったけど、姉ちゃんにやるよ!それと、不思議な夢を見たんだ。」
と言って、手の平に乗せて差し出した。
姉はびっくりした顔をして、病室のテレビ台の引き出しを開けて、何かを掴み取り出した。それは…
「タケル!守ってくれてありがとう!」
「ヒ、ヒ、ヒムカ…。」
引き出しから出てきた物は、少年が持っている物と同じ青い管玉だった。それも、二つをつなげるとちょうど一つになり、13個目の管玉だったのである。
姉は、自転車で丘の下の小道を通って、転んだ時に片方が割れている青い管玉を拾っていた。
そして、少年が同じ片方の割れた管玉を拾い、その日の夜、姉も少年も同じ時間に同じ夢を見ていたのだ。
発掘された墳丘墓の女性らしい甕棺に入った人骨は、卑弥呼よりももっと歳上のものらしいと考古学者は言っている。
いまだに発見されていない卑弥呼とその弟は、何処に眠っているのだろう。
その当時、邪馬台国に関する遺跡ではないかとも言われて、九州王朝説論争にまた火が付いたのである。この物語は、吉野ヶ里遺跡が発見された頃の不思議な物語である。
ある日の夕方、吉野ヶ里の小高い丘で元気よく遊んでいる中学生の子供達がいた。その中の一人の少年が、何かにつまずいて転んで足を怪我してしまう。
倒れた拍子に身をかばおうと、咄嗟に地面に手をつき、なにかを無意識に握りしめていた。
「おい、大丈夫か?」と友達の一人が声をかけた。
「大丈夫!」と返事はしたものの右足の膝を怪我してGパンに血が滲んでいた。
その返事を聞いて、友達は少年にまた声をかけた。
「そう言えば、お前の姉ちゃんも怪我してたなぁ…。姉弟おそろいで、仲の良い事。」
その少年には三つ上の姉がいて、この下の道を自転車で通っている時に、転び足を骨折する大怪我をしていた。
少年は、怪我をしたため、友達たちと早めに別れて家に帰った。服を着替え、怪我した膝にカットバンを貼り、脱いだ服を片付けようとGパンを取った時にポケットに何か入っているのに気づいた。それは、倒れた時に咄嗟に握りしめた物だった。青いガラス製の管のような物で片方が割れていた。
夕飯とお風呂を済ませて、傷口に薬をぬり、明日の宿題を片付けてベットに入った。しばらくして、その足の傷が、痛みだしうなされてしまう。そして、いつの間にか眠ってしまった。
少年は深い眠りに落ちて行くその間に、何か声が聞こえて来た。
「ねぇ、助けて下さい。お願いです…」と言う女性の声に、少年はゆっくり目を開けた。そこは、学校の教科書によく載っている弥生時代のもののような櫓の中だった。そして、まわりの景色もそこに居る人達の身につけている服も教科書の中の絵にあるようなものだった。
「おぉ…、目が覚めたか!タケル(武)!」と老婆が声を上げた。
「タケル? 」と小さくつぶやき声の方を向いた。そこには、一人の老婆と数人の大人達がいて、その櫓の中の一段高くなったところに、さっきの声の主だろう女性がいた。少年がいるところからは、その女性の顔はよく見えなかった。
女性は、ヒムカ(日向花)と言い、タケルは弟である。老婆は、不思議な力を持つ祈祷師で、何やら体じゅうを装飾し、両腕には大きな貝殻を繰る抜いた腕輪みたいなものが幾つも付けてあり、村人からは、神様みたいに崇められていた。
そして、ヒムカとタケルのおばあちゃんでもあるのだ。父と母は、この村を最初に築き上げたが、いく度となく起こる戦いですでに亡くなっていた。
タケルが目が覚めたのは、老婆がお祈りと呪文のような言葉をかけたからだっ
た。
「ここは何処ですか?あなた達は…?」と少年は声を出した。
「まだ、戦いの後で、正気に戻ってないようじゃ」と老婆がつぶやき、大人の一人がその後に話しかけてきた。
「タケル様、先ほどは勇者のような戦いでしたよ。」
大人達は、先ほどの戦いの話をしている。どうやらタケルは、大人達と一緒に戦ったらしく、姉のヒムカを守りその時に倒れて気を失い、老婆の何やら不思議な力で助かったと皆んなは、思っているようだ。
「ぼ、僕は、戦ったの?」
そう、小さい声でつぶやいた。
ヒムカや、老婆を含め100人程が暮らす村は、とても恵まれた場所にある。北には豊富な農作物が取れる畑がつくられ、真ん中の小高い丘には、竪穴式住居の集落がある。南に下ると広い海があり、海産物も取れる。
両親が築き上げたこの村の恵まれた立地は、他の勢力を強めている部族から狙われていて、村人達は、いつかは大きな戦いがおこり、この場所が奪われてしまうのではないかと恐れていた。そんな話しを聞き時間が経つにつれて、少年は夢を見ているのではなく、この村に生まれ育ってきたのだと思うようになっていった。また、ヒムカは、日増しに能力を高めて行き、いつしか村をまとめるようになって行った。そして、老婆は、ヒムカをこの村の王に任命した。
それから数日が経ち、ヒムカは自分で作った青い管玉の首飾りを、老婆に力を入れてもらい、弟であるタケルに渡すように頼んだ。老婆は祀られていた一本の青銅製の剣とその青い管玉の首飾りを渡した。それから、老婆は、タケルに言った。
「この剣を持つ者は、勇者であり、青い管玉を身に付けた者は、この村の王、ヒムカを最後まで守ることを誓わなければならない。」
タケルは、右手に剣を持ち、管玉の飾りを、自分の首に付けて、老婆に声を返した。
「はい!この村と王を守ってみせます。」
王ヒムカは、村を守るために男たちを集め、この村の周りに二重の環濠を造り、その周りに柵を巡らせることと、丘の一番高いところに、物見櫓を作るよう指示を出した。タケルは、ほかの男達を集め、戦い方と武器作りの指示をだし、一緒に準備を進めた。
そして、その戦いの日がやって来た。
今までとは違う数の敵の兵士が近づいて来るのが物見櫓から見ることが出来た。
「て、敵がきたぞ!」と櫓の方から大きな声が聞こえた。
「タケル、準備はいいか?」と老婆がすぐに声をかけてきた。
「はい、この剣と管玉の誓いで、力が湧いてきました。必ず守ってみせます。」
敵は、二重に掘られた環濠と柵により中には入って来れない。一箇所だけ小さい丘に通じる路があるが、敵がそこを通ることを予測して罠を仕掛けてある。深く掘られた落とし穴の底には、木の枝で作った槍を何本も立ててある。この落とし穴は大成功だった。そして、その罠に落ちなかった敵とタケルの最後の戦いが始まった。村を守るため、その村をまとめ築いてきたヒムカいや姉を守るために…。
その姉から貰った青い管玉の力なのか、自分には到底無いはずの不思議な力が備わっていた。
タケルは、敵を丘の上まで誘い、漲る力で敵を次々と倒していった。
「あと一人だ、いくぞ!」と自分に声をかけ、向かっていた。
激しい戦いは終わり、ヒムカの村は守られた。何人もの怪我をした男たちが、物見櫓の下に集まり、老婆が祈りと呪文をかけている。そして、その櫓の真ん中には、ヒムカが立っていた。ヒムカは、勇敢に戦った男たちをねぎらい、それを支えた女たちに優しく声をかけていた。しばらくして、ヒムカも老婆も村人も、弟のタケルがいないことに気付いた。
タケルは、小高い丘の側で倒れていた。最後の敵と相打ちになったのである。倒れている側には、青銅の剣と青い管玉が首からはずれ繋いであった紐も切れてバラバラに落ちていた。
ヒムカは、タケルの顔を見て、涙を流しながら「しっかりして!お願い目を開けて!」と何度も何度も体を揺さぶりながら声をかけ続けた。王になって、こんなに近くで弟の顔を見るのは、初めてだった。
そして、タケルは、ゆっくり目を開けた。
そこには、さっきまでの風景ではなく、いつもと変わらない自分の部屋の中だった。目の前には、母親の顔があった。怖い夢を見てうなされもがいていたらしく、その声と音に心配しておこしにきてくれたのだった。
少年は、そこで夢を見ていたことに気づいた。あまりにもリアルな不思議な夢だったけど、その夢のことは、親にも友達にも話さなかった。
そして、一週間が経ち土曜日の昼過ぎ、いつもの友達がまた遊びに行こうとやってきた。この前のあの丘のところで遊ぶことになり、皆んなで向かった。
しかし、そこにはもう入ることが出来なかった。立入禁止の看板が立っていて、柵で囲まれていた。そこからは、二つの甕棺が発掘され。一つは、女性だろうと思われる人骨が埋葬され、勾玉や鏡などの副葬品と腕には貝殻をくり抜いた腕輪をしていた。もう一つには、たくさんの青いガラス製の管玉と剣だけが埋葬されていて、人の骨は入っていなかった。
もともと埋蔵文化財があると思われていた場所だったのである。
次の日の新聞に大きく記事が載っていた。邪馬台国は九州にあった?という見出しと甕棺から青銅製の剣と青いガラス製の管玉が12個出土したが、その中には埋葬された人骨が入っていなかった。それが謎であるということと、剣には戦った跡が残っていたらしく、管玉は戦った勇者が身に付けていたはずだが、数がおかしいと書かれていた。普通は奇数で、勇者の階級によって、7、9、11、13個なのだと考古学者の持論も書かれていた。
少年は、その記事と一緒に乗っていた写真を見て、ある物を思い出した。そして、慌てて自分の部屋に戻り、机の引き出しを開けた。そこには、前に遊んで怪我した時に咄嗟に握りしめていた物が入っていた。
それは、割れてはいたが、あの発掘された青い管玉と同じ物だった。
そして、またそれを握りしめた。すると一週間程前に見た夢が頭の中を駆けめぐりはじめ、胸が高鳴って行くのを感じ、思わず「うぉぉぉ!」と叫んでしまった。
その声が聞こえたのか、母親が部屋に入ってきた。「どうしたの!そんなに大声を出して!」と聞かれ、「いや、な、何でもない…」と冷静に答えた。
そして、母親は、入院している姉の話を始めた。
「熱も下がりだいぶ良くなったみたいだから、お見舞いにでも行ったら…。一度も顔を出してないでしょ。」
「分かったよ。行くよ。気になる事もあるし…。」
「気になるんだったら、早く行けばいいのに…。」と、母親との会話を終えて、姉が入院している病院へ向かった。
姉は、ひと月ほど前に、あの丘のそばで怪我をして足を骨折した。怪我したところからバイキンが入ったらしく、高熱が出たのでそのまま入院することになってしまった。でも今では、骨もつながり、熱も下がったので、退院も近いようだ。
病院に着き、姉の病室へ向かった。個室のドアを開け中に入った。姉は、ベッドの上で身体を起こして新聞を見ていた。
「姉ちゃん…」と声をかけた。
「遅いなぁ、来るのが…もうすぐ退院するのに…」と、元気な姉の声に少しホッとした。
「ゴメン。あっ、これ…」とポケットに入れていたあの青い管玉を取り出し、夢の話しをしようと思った。
「僕の宝物にしょうと思ったけど、姉ちゃんにやるよ!それと、不思議な夢を見たんだ。」
と言って、手の平に乗せて差し出した。
姉はびっくりした顔をして、病室のテレビ台の引き出しを開けて、何かを掴み取り出した。それは…
「タケル!守ってくれてありがとう!」
「ヒ、ヒ、ヒムカ…。」
引き出しから出てきた物は、少年が持っている物と同じ青い管玉だった。それも、二つをつなげるとちょうど一つになり、13個目の管玉だったのである。
姉は、自転車で丘の下の小道を通って、転んだ時に片方が割れている青い管玉を拾っていた。
そして、少年が同じ片方の割れた管玉を拾い、その日の夜、姉も少年も同じ時間に同じ夢を見ていたのだ。
発掘された墳丘墓の女性らしい甕棺に入った人骨は、卑弥呼よりももっと歳上のものらしいと考古学者は言っている。
いまだに発見されていない卑弥呼とその弟は、何処に眠っているのだろう。