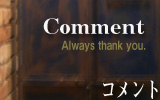この街に来て三度目の夏が来た。毎日、うだる様な熱さは何とかならないものか。
こういう日は、冷凍庫で霜が付いたグラスによく冷えたビールを注いで一気に飲むのが一番だ。と考えながら、あのBARへ向かった。
今日は、やっと彼女も一緒・・・。いや、遅れて行くからとメールが入ってきた。
まぁ、彼女が来るまでの間、前回の続きを聞かなくては・・・。
「こんばんは!」と重い年期の入った扉を静かに開けた。
『いらっしゃいませ!』とママの声がしたあと、『いらっしゃい!』とマスターからも声が聞こえた。
何やら、今日は忙しそうである。今来たばかりの三人の女性客がカウンターに、そして、テーブル席には、一時間ぐらいなるのだろう。灰皿には吸殻がたまり、また新しいタバコに火をつけた中年の男性とその前に若い女性が座っている。
「忙しいね。」
『珍しいでしょ。』とママから声がし、三人の女性の注文を聞き、マスターに伝えた。
『もうすぐ、落ち着くから、ちょっと待ってて下さいね。』とまた声がしたあと、僕の前に
コースターといっしょに思い切り冷えたビールが出てきた。
「おぅ、これこれ、飲みたかったんですよ。グラスまでギンギンに冷えたビールが・・・。」
「ウッ、美味いね。夏はこれだね。」
“ですよね。”と言わんばかりにチラッと僕の方を見てニコッとマスターが笑っていた。
しかし、よく分かるね僕の飲みたいものが。いや、この熱さじゃみんな考える事は同じなのだろう。それにしても、マスターとママがバタバタと仕事をしている姿はめったに見れないかもしれない。ママがオーダーを聞きマスターが飲み物をつくり、その間に、おつまみをママが用意しお客様の前に運ぶ。そして、出来上がった飲み物をマスターがそれぞれのコースターの上に運ぶ。
動きに無駄がない。マスターとママの息もピッタリ合っている。僕の前に出てきたビールもちゃんと計算されて出て来たに違いない。
『すみませんね。バタバタしてて・・・。』と女性にカクテルを出し終えて、少し落ち着いた様子でマスターから声がした。
「いえいえ、ビールが出てきて感激していたところです。」
『実は、私も飲みたくてね。ビールが・・・。』
「どうぞ、飲んで下さい。僕がおごりますよ。ママもね。」
『ありがとうございます。ところで、今日はご一緒じゃ・・・。』
「か、彼女ですか。メールが来て、先に行っててくれって・・・。」
『そうですか。』と話しながら、マスターは、いつの間にか片手に冷えたビールを握りしめていた。
「あっ、ママは?」
『例の・・・。』
「猫の世話ですね。」
『すみません。』
「ところで、例の話しの続きだけど・・・。」と言ったときに、テーブル席のカップルの方から「帰るよ!」と声がした。マスターはすぐにそのお客様のところに行き、ニコニコ笑いながら挨拶を交わして、外まで見送りをした。そして、空になったグラスを下げながらカウンターの中に戻った。
『この前の“ブルームーン”の話しね?』と、洗い物を片付けながら声がした。そして、続けてまた声がした。
『その前に、お代わりをしましょうか?』
「はい。何かウイスキーを・・・。」
『かしこまりました。美味いウイスキーがあるんですよ。』と、バック棚から一本のウイスキーを取り出しカウンターの上に置いた。それから大き目の氷が一個入れられたロックグラスにそのウイスキーが注がれ、僕のコースターの上に置かれた。
『はい。どうぞ。』
「美味しそうなウイスキーですね。」
『マッカランの18年物です。私も好きなんですよ。』
「うん、美味い!」
『でしょ・・・。』
「ところで・・・。」
『はい。分かってますよ。お互い二度目だというとこまででしたね。』
「そうそう、“二度目”まででした。」
『で、ちょうどその“二度目の満月(ブルームーン)”の日に、彼女が一人で来てまして、他にお客さんも居なくてね、カクテルのブルームーンを飲みながらバツイチ同士、妙に盛り上がりましてね。』
「いい感じになったんですね。」
『まぁですね。そして、彼女が帰る時に、見送ろうと一緒にお店の外まで出たんですよ。そしたら急に、帰り道を照らす二度目の満月に向かって“二回目は幸せになるぞぉ!”て叫んだんですよ。』
「へぇ、なんか、ドラマみたいじゃないですか。で、マスターはどうしたの?」
『どうって、それを聞いて私も叫びましたよ。“同じ言葉を・・・”』
「“同じ言葉”ですか?」
『い、いや、ちょっと違ってました。“二回目は幸せにするぞぉ!”でした。』
「それが決め台詞になったんですね。」
『まぁ、そういうことです。』とマスターが話し終えた時、ママが二階から降りて来た。
「ママ!聞きましたよ。この前の続き・・・。“願い事”が叶ったんですね。」
『は、はい。2回目にやっとね。』とちょっと照れくさそうな笑みを浮かべながらママが答えた後、三人組の女性から「お代わり」の注文が入った。
ママが空になったグラスを下げ、お代わりのオーダーを聞いて、マスターがカクテルをつくりだした。年期の入ったリズミカルなシェーキングだ。一瞬静まり返った後、透き通るような金属音が店内に響き渡った。バーテンダーの仕事の中で一番格好よく見えるところだろう。
見ているだけで美味しそうな感じがするし、飲みたくなる。
とその時、僕の内ポケットで携帯が光りながら動き出した。
彼女からのメールだ。三行ほどの短い文章だった。
「マスター。今日はこれで帰ります。」
『待ち合わせだったんじゃ・・・。』
「今日は来れなくなったって今メールが来て・・・。」
『そ、そうですか。残念です。お会いできると思っていたんですが・・・。』
こういう日は、冷凍庫で霜が付いたグラスによく冷えたビールを注いで一気に飲むのが一番だ。と考えながら、あのBARへ向かった。
今日は、やっと彼女も一緒・・・。いや、遅れて行くからとメールが入ってきた。
まぁ、彼女が来るまでの間、前回の続きを聞かなくては・・・。
「こんばんは!」と重い年期の入った扉を静かに開けた。
『いらっしゃいませ!』とママの声がしたあと、『いらっしゃい!』とマスターからも声が聞こえた。
何やら、今日は忙しそうである。今来たばかりの三人の女性客がカウンターに、そして、テーブル席には、一時間ぐらいなるのだろう。灰皿には吸殻がたまり、また新しいタバコに火をつけた中年の男性とその前に若い女性が座っている。
「忙しいね。」
『珍しいでしょ。』とママから声がし、三人の女性の注文を聞き、マスターに伝えた。
『もうすぐ、落ち着くから、ちょっと待ってて下さいね。』とまた声がしたあと、僕の前に
コースターといっしょに思い切り冷えたビールが出てきた。
「おぅ、これこれ、飲みたかったんですよ。グラスまでギンギンに冷えたビールが・・・。」
「ウッ、美味いね。夏はこれだね。」
“ですよね。”と言わんばかりにチラッと僕の方を見てニコッとマスターが笑っていた。
しかし、よく分かるね僕の飲みたいものが。いや、この熱さじゃみんな考える事は同じなのだろう。それにしても、マスターとママがバタバタと仕事をしている姿はめったに見れないかもしれない。ママがオーダーを聞きマスターが飲み物をつくり、その間に、おつまみをママが用意しお客様の前に運ぶ。そして、出来上がった飲み物をマスターがそれぞれのコースターの上に運ぶ。
動きに無駄がない。マスターとママの息もピッタリ合っている。僕の前に出てきたビールもちゃんと計算されて出て来たに違いない。
『すみませんね。バタバタしてて・・・。』と女性にカクテルを出し終えて、少し落ち着いた様子でマスターから声がした。
「いえいえ、ビールが出てきて感激していたところです。」
『実は、私も飲みたくてね。ビールが・・・。』
「どうぞ、飲んで下さい。僕がおごりますよ。ママもね。」
『ありがとうございます。ところで、今日はご一緒じゃ・・・。』
「か、彼女ですか。メールが来て、先に行っててくれって・・・。」
『そうですか。』と話しながら、マスターは、いつの間にか片手に冷えたビールを握りしめていた。
「あっ、ママは?」
『例の・・・。』
「猫の世話ですね。」
『すみません。』
「ところで、例の話しの続きだけど・・・。」と言ったときに、テーブル席のカップルの方から「帰るよ!」と声がした。マスターはすぐにそのお客様のところに行き、ニコニコ笑いながら挨拶を交わして、外まで見送りをした。そして、空になったグラスを下げながらカウンターの中に戻った。
『この前の“ブルームーン”の話しね?』と、洗い物を片付けながら声がした。そして、続けてまた声がした。
『その前に、お代わりをしましょうか?』
「はい。何かウイスキーを・・・。」
『かしこまりました。美味いウイスキーがあるんですよ。』と、バック棚から一本のウイスキーを取り出しカウンターの上に置いた。それから大き目の氷が一個入れられたロックグラスにそのウイスキーが注がれ、僕のコースターの上に置かれた。
『はい。どうぞ。』
「美味しそうなウイスキーですね。」
『マッカランの18年物です。私も好きなんですよ。』
「うん、美味い!」
『でしょ・・・。』
「ところで・・・。」
『はい。分かってますよ。お互い二度目だというとこまででしたね。』
「そうそう、“二度目”まででした。」
『で、ちょうどその“二度目の満月(ブルームーン)”の日に、彼女が一人で来てまして、他にお客さんも居なくてね、カクテルのブルームーンを飲みながらバツイチ同士、妙に盛り上がりましてね。』
「いい感じになったんですね。」
『まぁですね。そして、彼女が帰る時に、見送ろうと一緒にお店の外まで出たんですよ。そしたら急に、帰り道を照らす二度目の満月に向かって“二回目は幸せになるぞぉ!”て叫んだんですよ。』
「へぇ、なんか、ドラマみたいじゃないですか。で、マスターはどうしたの?」
『どうって、それを聞いて私も叫びましたよ。“同じ言葉を・・・”』
「“同じ言葉”ですか?」
『い、いや、ちょっと違ってました。“二回目は幸せにするぞぉ!”でした。』
「それが決め台詞になったんですね。」
『まぁ、そういうことです。』とマスターが話し終えた時、ママが二階から降りて来た。
「ママ!聞きましたよ。この前の続き・・・。“願い事”が叶ったんですね。」
『は、はい。2回目にやっとね。』とちょっと照れくさそうな笑みを浮かべながらママが答えた後、三人組の女性から「お代わり」の注文が入った。
ママが空になったグラスを下げ、お代わりのオーダーを聞いて、マスターがカクテルをつくりだした。年期の入ったリズミカルなシェーキングだ。一瞬静まり返った後、透き通るような金属音が店内に響き渡った。バーテンダーの仕事の中で一番格好よく見えるところだろう。
見ているだけで美味しそうな感じがするし、飲みたくなる。
とその時、僕の内ポケットで携帯が光りながら動き出した。
彼女からのメールだ。三行ほどの短い文章だった。
「マスター。今日はこれで帰ります。」
『待ち合わせだったんじゃ・・・。』
「今日は来れなくなったって今メールが来て・・・。」
『そ、そうですか。残念です。お会いできると思っていたんですが・・・。』