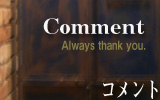今日は出張だった。予定よりも早く仕事も終わり、彼女とゆっくり逢うことができる日だと思っていたが、明日早いからダメだと断られてしまった。
この街でやっと見つけた、あの店に一緒に行こうと思っていたが、またしても一人で足を運ぶこととなった。満月の月明かりの中、路地裏のバーに向かった。
「こんばんは、まだいいかなぁ?」
『いらっしゃいませ。まだだいじょうぶですよ。』と、今日はママが迎えてくれた。
「珍しいね…。ママだけなの?」
『いいえ、猫の世話です。たまにはしてもらわないとねぇ…。』
「マスターが猫の世話ですか!」
「しばらく、下りてこなくていいよ。って伝えて!」
『もう、下りてきますよ。それで、何をお出ししましょうか?』
「ママのお奨めでもいただこうかなぁ…。」と、答えた時には、もうマスターがカウンターの中に、目じりが下がった優しい顔で立っていた。
「マスター!いつの間に下りてきたの?」
『すみませんね。猫みたいで…。』
とマスターが答えたあと、ママが、何やら目で合図を送ると、カクテルを作り出した。手際よく、さっそうとシェーカーを振り、冷やしてあったカクテルグラスに薄紫色の綺麗なカクテルが注がれ、僕の前へと運ばれてきた。
『はい。どうぞ!』
「おぅ、綺麗なカクテルですね。」と、僕が呟くと、ママが笑みを浮かべ、また、声が聞こえた。
『私の一番好きなカクテルですよ。マスターと結婚する前によく飲んでいたの…。』
「マスターとの思い出のカクテルですか…。」
『マスターの作るこのカクテルが一番好きでね。』と、マスターの顔を横目で見ながら教えてくれた。そして、その後に付け足すようにママの口がまた動き始めた。
『今日は、珍しい日なんですよ。』
「何が、珍しいの!僕はいつも一人だけどなぁ…。」
『お客様の事じゃなくて…。今夜の満月…。』
「満月?がどうしたの?」
『今月は、二度目の満月の日なんですよ。』
「二度目!そういえば、僕も今月、ここに来るのが確か二度目だ…。」
『あら、そうですね。』とママが答えた後に低い声で、マスターが僕とママの会話の中に入って来た。
『“ブールムーン”って言うんですよ。』
「このカクテルの名前なんですか。」
『そうですね。カクテルもだけど、同じ月にやってくる二度目の“満月”の事も…。そして、それに願い事を唱えると叶うと言われているんですよ。』
と、ニコニコしながらマスターが教えてくれた。
「へぇ…。そうなんだ…。」としばらく会話が途絶え、静かな空気の中で、そのカクテルを口に運んだ。甘酸っぱくて、香りがいいカクテルだ。女性が好みそうな味がする。
きっと、ママもこの香りと色が好きなんだろう。
カクテルを半分ほど飲み終えたときに、ママがまた、僕に静かな口調で話しかけてきた。
『結婚してからは、一度も“ブルームーン”を飲んでないんですよ。』
「僕がおごりますよ、一緒にどうですか!」
『ありがとうございます。気持ちはうれしいですけど、やめときますね。今日は・・・。』
「こんなに美味しいのに、どうして…。」「昔をあまり思い出したくないとか?」
『いいえ、そんなことはありませんよ。』とだけ残して、いつの間にか、カウンターからその姿が消えていた。
「ママは?」
『すみませんね。定刻の猫の世話で…。』とマスターから声がした。
「そ、そうなんですね…。」
「ところで、このカクテルって、何か、他に秘密があるの?」
『…。私が言うのも…。』と言いながら、ゆっくり口を動かした。
『実はね。家内とは、再婚なんです。それも、お互い二度目なんですよ。』
「な、なんか悪いこと聞いたみたいですね。」
『いいんですよ。そのうち分かることだし、それに今は、充分幸せですから…。』
「で、ブルームーンは・・・。」
『その前に、お代わりは?』
「そ、そうだね。じゃぁ“ハイボール”をいただきます。」
『はい!かしこまりました。』と言って、冷蔵庫から冷して置いた“角瓶”を取り出し、手際よくハイボールをつくり、僕の前の空のカクテルグラスと差し替えた。
『はい、どうぞ。』
「いただきます。美味いね。やっぱり。」
ここのマスターのつくるハイボールもまた絶品だ。それと手際のよさがとても奇麗に感じる。長年の経験がそうさせているのだろう。
意識しているのではなく、自然なところがまたいいのだ。
「あっ!もうこんな時間ですか!明日、仕事じゃなかったら、“続きの話し”を聞きたいけど、今日は、このハイボールで帰るとします。」
『ありがとうございます。いつも。』
「今度は、二人で来ますよ。ブルームーンの続きを聞きに・・・。」
この街でやっと見つけた、あの店に一緒に行こうと思っていたが、またしても一人で足を運ぶこととなった。満月の月明かりの中、路地裏のバーに向かった。
「こんばんは、まだいいかなぁ?」
『いらっしゃいませ。まだだいじょうぶですよ。』と、今日はママが迎えてくれた。
「珍しいね…。ママだけなの?」
『いいえ、猫の世話です。たまにはしてもらわないとねぇ…。』
「マスターが猫の世話ですか!」
「しばらく、下りてこなくていいよ。って伝えて!」
『もう、下りてきますよ。それで、何をお出ししましょうか?』
「ママのお奨めでもいただこうかなぁ…。」と、答えた時には、もうマスターがカウンターの中に、目じりが下がった優しい顔で立っていた。
「マスター!いつの間に下りてきたの?」
『すみませんね。猫みたいで…。』
とマスターが答えたあと、ママが、何やら目で合図を送ると、カクテルを作り出した。手際よく、さっそうとシェーカーを振り、冷やしてあったカクテルグラスに薄紫色の綺麗なカクテルが注がれ、僕の前へと運ばれてきた。
『はい。どうぞ!』
「おぅ、綺麗なカクテルですね。」と、僕が呟くと、ママが笑みを浮かべ、また、声が聞こえた。
『私の一番好きなカクテルですよ。マスターと結婚する前によく飲んでいたの…。』
「マスターとの思い出のカクテルですか…。」
『マスターの作るこのカクテルが一番好きでね。』と、マスターの顔を横目で見ながら教えてくれた。そして、その後に付け足すようにママの口がまた動き始めた。
『今日は、珍しい日なんですよ。』
「何が、珍しいの!僕はいつも一人だけどなぁ…。」
『お客様の事じゃなくて…。今夜の満月…。』
「満月?がどうしたの?」
『今月は、二度目の満月の日なんですよ。』
「二度目!そういえば、僕も今月、ここに来るのが確か二度目だ…。」
『あら、そうですね。』とママが答えた後に低い声で、マスターが僕とママの会話の中に入って来た。
『“ブールムーン”って言うんですよ。』
「このカクテルの名前なんですか。」
『そうですね。カクテルもだけど、同じ月にやってくる二度目の“満月”の事も…。そして、それに願い事を唱えると叶うと言われているんですよ。』
と、ニコニコしながらマスターが教えてくれた。
「へぇ…。そうなんだ…。」としばらく会話が途絶え、静かな空気の中で、そのカクテルを口に運んだ。甘酸っぱくて、香りがいいカクテルだ。女性が好みそうな味がする。
きっと、ママもこの香りと色が好きなんだろう。
カクテルを半分ほど飲み終えたときに、ママがまた、僕に静かな口調で話しかけてきた。
『結婚してからは、一度も“ブルームーン”を飲んでないんですよ。』
「僕がおごりますよ、一緒にどうですか!」
『ありがとうございます。気持ちはうれしいですけど、やめときますね。今日は・・・。』
「こんなに美味しいのに、どうして…。」「昔をあまり思い出したくないとか?」
『いいえ、そんなことはありませんよ。』とだけ残して、いつの間にか、カウンターからその姿が消えていた。
「ママは?」
『すみませんね。定刻の猫の世話で…。』とマスターから声がした。
「そ、そうなんですね…。」
「ところで、このカクテルって、何か、他に秘密があるの?」
『…。私が言うのも…。』と言いながら、ゆっくり口を動かした。
『実はね。家内とは、再婚なんです。それも、お互い二度目なんですよ。』
「な、なんか悪いこと聞いたみたいですね。」
『いいんですよ。そのうち分かることだし、それに今は、充分幸せですから…。』
「で、ブルームーンは・・・。」
『その前に、お代わりは?』
「そ、そうだね。じゃぁ“ハイボール”をいただきます。」
『はい!かしこまりました。』と言って、冷蔵庫から冷して置いた“角瓶”を取り出し、手際よくハイボールをつくり、僕の前の空のカクテルグラスと差し替えた。
『はい、どうぞ。』
「いただきます。美味いね。やっぱり。」
ここのマスターのつくるハイボールもまた絶品だ。それと手際のよさがとても奇麗に感じる。長年の経験がそうさせているのだろう。
意識しているのではなく、自然なところがまたいいのだ。
「あっ!もうこんな時間ですか!明日、仕事じゃなかったら、“続きの話し”を聞きたいけど、今日は、このハイボールで帰るとします。」
『ありがとうございます。いつも。』
「今度は、二人で来ますよ。ブルームーンの続きを聞きに・・・。」