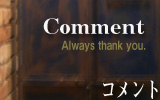この街に転勤してきて1年半が過ぎた。
新しい職場にも慣れ、他の社員達とも適度にコミュニケーションが取れるようになった。
仕事に少し余裕ができたおかげで、すっかり忘れていたのを思い出した。
確か、この街に小さな古いBARがあると地元の友人に教えられていたことだった。
今日の目的は、その店を探すことだ。
空き店舗が目立つ中心商店街のアーケードの中を入ってすぐの狭い路地を入ったところだと聞いていたが・・・。
「この辺りのはずだが…。」
「ここかなぁ・・・、あった! ここだ、ここだ。」
緑色のアクリルの看板に白抜きで「BAR」と書いてある。
間違いなくここである。
木造の2階建てで、1階がバー。2階は住居になってるみたいだ。入り口には鉄板が張られている。その錆び具合が古さを引き出している。
さて、重そうな扉を開けて入ってみることにしますか。
『いらっしゃい!』
「あ、あの〜、一人ですが・・・。」
『どうぞ!お好きなところに。』
年は60過ぎぐらいだろうか、白髪交じりにメガネを掛け、黒い蝶ネクタイ姿の男が一人、他にお客さんはいないようである。店は、落ち着いた雰囲気だ。木目が見える板を張り合わせたカウンターに7席とその後ろに4人がけのテーブルが2つあり、バック棚は、三段になっていて見たことも無いボトルがズラリと並べられている。
「マスター!一人でされてるんですか?」
『いいえ。家内も一緒ですよ。今、猫の世話で2階に・・・。』
「そうですか。」
「転勤でこの街に来て、友人に教わって来たんですよ。ここに・・・。」
『そうですか。ありがとうございます。』『で、何をお出ししましょう?』
「そうですね。さっぱりしたカクテルでも・・・。」
『ジントニックでもよろしいですか?』
「は、はい!」
ここのマスターは、手際よく、材料をカウンターの上に並べ、ジントニックを作り出した。
ジンは、冷凍庫から出したのだろう。ボトルいっぱいに霜が付いている。美味いカクテルを味わえそうである。
『はい!どうぞ!』とBARとさりげなく印刷された丸いコースターの上にカクテルが静かに置かれた。
ここを探すのに正直疲れていたし、喉が冷たいアルコールを欲しがっていた。
「おぉ、美味い!」「いやぁ、飲みたかったんですよ。美味いカクテルが・・・。」
『そうですか、ありがとうございます。』
「ところで、看板には“BAR”としか書かれていないですね。」
『はい、よく聞かれるんですよ。名前はないのか?って・・・。』
「でも、なんか、いい感じじゃないですか。」
『そう言っていただけると、ありがたいですね。』
『昔はBARと呼べる店は、ここだけだったんですよ。』
「そうなんですね。」
『そろそろ、家内も降りてくるころですよ。猫好きでね・・・。まぁ、私も嫌いじゃないんですけど・・・。』
「へぇ〜。」「夫婦そろって猫好きなんだ!」
『そうですね。』『店にとっては、招き猫ですかね・・・。』
「それにしても、マスターのジントニック、美味いですね!」
『そうですか。それは、それは・・・。約40年、頑張って来ましたしね。』
「マスター!今日はご馳走様。また、寄らせてもらいますよ。場所も分かったことだし・・・。」
『すみませんね。内のがまだ下りてこなくて・・・。』
「次の楽しみということで・・・。」
『ありがとうございました。また、よろしくお願いします。』
新しい職場にも慣れ、他の社員達とも適度にコミュニケーションが取れるようになった。
仕事に少し余裕ができたおかげで、すっかり忘れていたのを思い出した。
確か、この街に小さな古いBARがあると地元の友人に教えられていたことだった。
今日の目的は、その店を探すことだ。
空き店舗が目立つ中心商店街のアーケードの中を入ってすぐの狭い路地を入ったところだと聞いていたが・・・。
「この辺りのはずだが…。」
「ここかなぁ・・・、あった! ここだ、ここだ。」
緑色のアクリルの看板に白抜きで「BAR」と書いてある。
間違いなくここである。
木造の2階建てで、1階がバー。2階は住居になってるみたいだ。入り口には鉄板が張られている。その錆び具合が古さを引き出している。
さて、重そうな扉を開けて入ってみることにしますか。
『いらっしゃい!』
「あ、あの〜、一人ですが・・・。」
『どうぞ!お好きなところに。』
年は60過ぎぐらいだろうか、白髪交じりにメガネを掛け、黒い蝶ネクタイ姿の男が一人、他にお客さんはいないようである。店は、落ち着いた雰囲気だ。木目が見える板を張り合わせたカウンターに7席とその後ろに4人がけのテーブルが2つあり、バック棚は、三段になっていて見たことも無いボトルがズラリと並べられている。
「マスター!一人でされてるんですか?」
『いいえ。家内も一緒ですよ。今、猫の世話で2階に・・・。』
「そうですか。」
「転勤でこの街に来て、友人に教わって来たんですよ。ここに・・・。」
『そうですか。ありがとうございます。』『で、何をお出ししましょう?』
「そうですね。さっぱりしたカクテルでも・・・。」
『ジントニックでもよろしいですか?』
「は、はい!」
ここのマスターは、手際よく、材料をカウンターの上に並べ、ジントニックを作り出した。
ジンは、冷凍庫から出したのだろう。ボトルいっぱいに霜が付いている。美味いカクテルを味わえそうである。
『はい!どうぞ!』とBARとさりげなく印刷された丸いコースターの上にカクテルが静かに置かれた。
ここを探すのに正直疲れていたし、喉が冷たいアルコールを欲しがっていた。
「おぉ、美味い!」「いやぁ、飲みたかったんですよ。美味いカクテルが・・・。」
『そうですか、ありがとうございます。』
「ところで、看板には“BAR”としか書かれていないですね。」
『はい、よく聞かれるんですよ。名前はないのか?って・・・。』
「でも、なんか、いい感じじゃないですか。」
『そう言っていただけると、ありがたいですね。』
『昔はBARと呼べる店は、ここだけだったんですよ。』
「そうなんですね。」
『そろそろ、家内も降りてくるころですよ。猫好きでね・・・。まぁ、私も嫌いじゃないんですけど・・・。』
「へぇ〜。」「夫婦そろって猫好きなんだ!」
『そうですね。』『店にとっては、招き猫ですかね・・・。』
「それにしても、マスターのジントニック、美味いですね!」
『そうですか。それは、それは・・・。約40年、頑張って来ましたしね。』
「マスター!今日はご馳走様。また、寄らせてもらいますよ。場所も分かったことだし・・・。」
『すみませんね。内のがまだ下りてこなくて・・・。』
「次の楽しみということで・・・。」
『ありがとうございました。また、よろしくお願いします。』